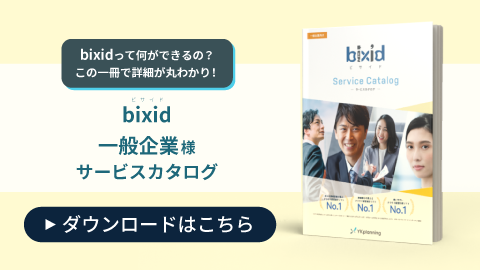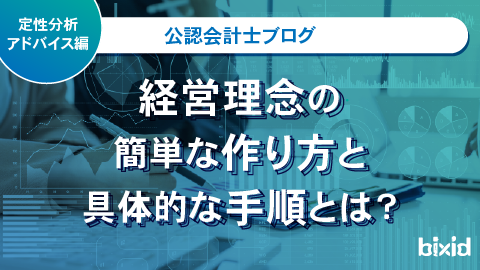CFOの役割、 求められる能力
企業経営をおこなっていくうえで非常に大切なポジションのひとつに、「CFO(最高財務責任者)」というものがあります。日本ではまだ浸透しきっておらず、CEO?CFO?COO?とクエスチョンマークで頭がいっぱいになってしまう方も多いかもしれません。
今回は、企業経営において今後より重要になっていくと考えられている「CFO」について解説します。
「CEO」「COO」と「CFO」の違い
本題に入る前に組織におけるさまざまな役職について簡単にご紹介します。
最もよく聞く役職として挙げられるのが「CEO(最高経営責任者)」ではないでしょうか。「Chief Executive Officer」の頭文字を取ったもので、経営の責任を担う立場です。
また、実質的なナンバー2である「COO(最高執行責任者)」は「Chief Operating Officer」の頭文字を取ったもので、CEOの下で実務・運営においての最高責任者という立場になります。
そのほかにも、「CTO(最高技術責任者)」「CMO(最高マーケティング責任者)」「CIO(最高情報責任者)」「CAO(最高総務責任者)」など各分野にもそれぞれ責任を担う立場の役職が設けられています。
組織規模が小さい場合は、役職を細分化するケースは少なく、CEOやCOOにあたる人が「CFOの役割をまとめて担う」というケースもあるでしょう。しかし、企業が成長していくためには強い組織づくりが必要不可欠です。まずは、各役職の役割や責任の範囲を検討してみてはいかがでしょうか。
CFOとは?意味と役割、管理部長との違い
さて、今回の本題となるCFOについてみていきましょう。
CFOとは、「Chief Financial Officer」の頭文字をとった略称で、日本語では「最高財務責任者」を指します。つまり、企業の財務に関する責任を担う立場のことです。 近年のグローバル化に伴い、各企業では以前にも増して「財務管理の透明性」が求められています。また、経営指標の決定の際には、欧米機関の投資家を中心とした株主の意見が重視されるようになりました。
近年のグローバル化に伴い、各企業では以前にも増して「財務管理の透明性」が求められています。また、経営指標の決定の際には、欧米機関の投資家を中心とした株主の意見が重視されるようになりました。
そのため日本の企業においても、世界基準に沿った財務管理をおこなわなければならないのが現状です。
財務戦略をいかに経営戦略に盛り込むかが、その企業が世界的に成功できるかどうかを握っていると言っても過言ではないでしょう。
そうなると、CFOの果たす役割は単に経理や財務管理に関わるものだけではなくなってきます。営業や管理、システム、など企業の様々な面に精通していなければ、その役割を全うすることは難しいと言えるでしょう。
日本における管理部長は、財務経理の立場から企業運営を管理するというイメージが強いのではないでしょうか。
一方で、アメリカでは、財務戦略を経営戦略の1つとして見なすことから、CFOを経営陣の一員としてとらえており、経営企画・IR、管理部、法務、ITなど、経営管理を統括する役員という役割があります。
そういった点が、管理部長とCFOの違いにあるといえます。
ビジネスのグローバル化が進む昨今、財務や経理の専門知識を基に、海外の企業と対等に資金調達やM&AをおこなうことができるCFOは、少しずつ重要な存在となってきています。
COOと並んで、CEOの右腕として企業成長のための経営戦略や財務戦略の立案、執行を担うなど、経営陣としての責任を負わなくてはならなくなったのです。
CFOに必要なスキル
重要度の高まりつつあるCFOですが、どのようなスキルが必要なのでしょうか?
先述したCFOに求められる役割が多岐にわたっているように、さまざまなスキルが求められています。 1.財務・会計などに関する専門知識・経験
1.財務・会計などに関する専門知識・経験
企業の財務戦略や予算管理、財務報告などを担当するため財務会計、経理、税務の専門知識やデータ分析能力が不可欠です。
2.マネジメント能力
さまざまな部署と連携・協力し会社の目標を達成する必要があるためマネジメント能力も重要です。また、財務戦略の立案や実行において、ビジョンや目標を明確に伝えチームを統率して成果を出すために、リーダーシップを発揮する必要があります。財務部門の人材育成やモチベーション向上にもリーダーシップが求められます。
3.コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力
ステークホルダーとの信頼構築や部下または他部門との連携や協力が欠かせないため、円滑な関係を築くことのできるコミュニケーション能力も重要です。また、ステークホルダーに対して財務情報などを分かりやすく伝え、適切な説明責任を果たす必要があるため、相手に配慮した効果的なプレゼンテーションをおこなうことも求められます。
4.リスク管理能力
企業が直面するさまざまな不確実性に対応するためのリスク管理能力も必要です。CFOはこうしたリスクに対して、適切な分析・評価・対策をおこなうことが求められます。そして危機的状況におかれた場合でも冷静に判断し、迅速に行動することが必要です。また、企業が財務面で健全な経営を続けていくために、CFOにはコストやコンプライアンスへの高い意識も必要となります。
5.グローバルな視点と語学力
CFOはグローバルな視点で経営をサポートする役割を担っており、さまざまな国や地域のビジネスパートナーとコミュニケーションを取る必要があります。多言語に対応できれば、より幅広い知識や経験を身につけることができ、自分の専門性や価値を高めることができます。
企業の成長ステージで違うCFOの役割
CFOが果たすべき役割は、属している企業の成長ステージによっても変わってきます。
◆スタートアップ期
企業の創業期において、CFOが担うべき最も重要な役割は「資金調達」になるでしょう。創業したばかりの企業は運転資金に余裕があるとは言えないため、ビジネスモデルにもよりますが、事業を成長させるために資金調達をおこなう場合が多いでしょう。金融機関から融資を受けるとなれば、財務諸表の整理や返済計画の作成などが必要になってきます。CFOの優劣によって成長速度に大きく差がつくと言えますね。
◆拡大期
拡大期においては、創業時よりも「資金管理」が重要性を増してきます。これは新たな従業員の雇用による人件費やオフィスの賃料、広告宣伝費、新たな商品やシステム開発費などのコストが増えるために他なりません。また、各部門に対しての適切な予算配分や、コストカット可能な部分の洗い出しなどをおこないながら資金計画を随時アップデートしていくこともCFOの重要な役割となってくるでしょう。
◆上場準備期
上場の準備をする頃までになると、CFOの業務は主に「内部統制構築」「監査法人・証券会社等の選定および渉外」となり、社内外でますますその重要性を高めます。ここに至るまでには、資金の問題などから外部に委託する企業もありますが、このフェーズまでやってくると社内に常任のCFOの存在が必要不可欠です。CFOもチーム制で分業する必要が出てくるため、チームをマネジメントする能力も必要になってくると言えます。
まとめ
馴染みのない単語だと敬遠しがちな経営用語。近年企業内で実質 ナンバー2になりつつありその存在感を増してきているCFOは、今のうちに覚えておきたい単語の1つです。
特に中小企業では、市場環境の急速な変化に対し、財務の側面においてスピーディーな判断が不可欠です。
そのためには、中小企業経営者は財務面で重要な意思決定を的確におこなうことができ、企業の成長を促進するような体制づくりが必要になるでしょう。
CFOを育成することは、単なる財務戦略の強化だけでなく、企業の将来の成功に直結します。早い段階でCFOの育成に取り組むことで、経営の安定性と成長の基盤を築くことができます。
中小企業の経営者のみなさま、今こそ、CFOの育成に積極的に取り組み、企業の持続可能な成功を確かなものにしましょう。

大学卒業後、金融機関のリテール営業からEY新日本有限責任監査法人での金融機関監査とIPO支援経験を積む。独立し税理士事務所を開業後、YKプランニング入社。現在は経営管理本部で予算管理とバックオフィス業務を統括。幅広い財務会計と金融の知識と経験を活かし、組織の成功に貢献するべく管理体制を強化中。
趣味はゴルフ・YouTubeで興味がない分野の動画をあえて見ること。