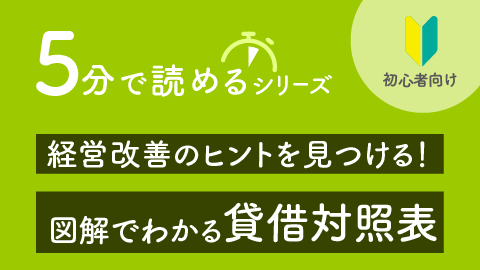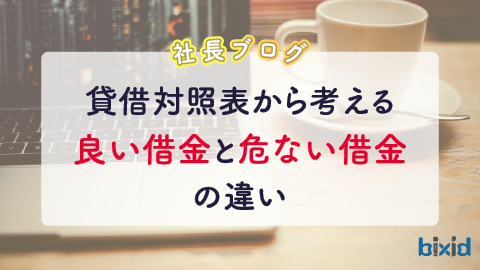流動比率・当座比率で企業の安全性を見極める方法
こんにちは、YKプランニング代表取締役社長の岡本です。
企業の財務状況を把握するには、貸借対照表(B/S)の読み解きは欠かせません。
貸借対照表に記載されている「資産」「負債」「自己資本」の構造を把握することで、会社の安全性や成長を支える基盤を評価することができます。
なかでも短期的な支払い能力を判断するうえで代表的な指標が、【流動比率】と【当座比率】です。
一見シンプルな指標ですが、その読み解き方次第で経営判断に大きな差が出ます。今回はこの2つの比率の違いを正しく理解し、適切に使い分けることで、財務の“今”をどのように見極めるかを考えていきましょう。
短期安全性の指標「流動比率」と「当座比率」
貸借対照表は、企業の「持っているもの」と「借りているもの(+自己資本)」を一覧できる構造になっています。
その中でも、1年以内に現金化される「流動資産」と、1年以内に支払い義務が発生する「流動負債」のバランスを見ることは、資金繰りの観点で非常に重要です。 企業が安定的に活動を続けるためには、「今ある資産で、すぐに返さなければならないお金をどれだけ賄えるか?」という視点が欠かせません。
企業が安定的に活動を続けるためには、「今ある資産で、すぐに返さなければならないお金をどれだけ賄えるか?」という視点が欠かせません。
そこで登場するのが【流動比率】と【当座比率】。
これらの指標を通じて、会社が短期的な支払い能力をどれだけ備えているかを見極めていくのが今回のテーマです。
流動比率の計算と読み解くコツ
まずは流動比率からご説明します。
計算式は以下の通りです。
【流動比率(%)】=流動資産 ÷ 流動負債 × 100
たとえば、流動資産が1,500万円、流動負債が1,000万円の場合、【流動比率】は
→ 1,500万円(流動資産) ÷ 1,000万円(流動負債) × 100 = 150%
一般的な目安としては150%以上が安全とされ、「短期的な支払い能力に問題なし」と評価されます。つまり、支払うべきお金に対して、1.5倍を超える“すぐ使える資産”がある状態が安全とされることを意味しています。
ここで注意したいのは、数値は高い方がいいとは限らないということです。数値が高いからといって「とても良い状態だ」と短絡的に判断しないようにしましょう。
その内訳に在庫の積み上がりや売掛金の長期滞留といった問題が潜んでいる可能性もあります。
そのため重要になるのが、「中身の吟味」です。
急な支払いが発生したときでも“本当に使える資産”で構成されているかを見るために、次に紹介する【当座比率】が役立ちます。
当座比率で何がわかる?流動比率との違いと目安
当座比率は、流動資産の中でも「すぐに現金化できるもの」のみに注目して算出します。計算式は以下の通りです。
【当座比率(%)】=当座資産 ÷ 流動負債 × 100
当座資産には、「現預金」「売掛金」「受取手形」など、即時性の高い資産のみが含まれます。
逆に、「棚卸資産(在庫)」や「前払金・前払費用」などは除外されます。
なぜ除外するのかというと、それらはすぐには現金化できず、場合によっては不良化や回収不能リスクがあるからです。
先ほどの例では、流動資産1,500万円の内訳が以下の通りだったとします。
「現 預 金」:300万円 ←当座比率に使う
「売 掛 金」:500万円 ←当座比率に使う
「棚卸資産」:700万円 ←当座比率には使わない
このとき当座資産は、300万円 + 500万円 = 800万円。
当座比率:800万円(当座資産) ÷ 1,000万円(流動負債) × 100 = 80%
この数字から、「見た目は安全(流動比率)だが、実際にはやや不安(当座比率)がある状態」と読み取れます。
なお、「当座比率の安全水準は100%以上」が目安とされています。
つまり、現金などすぐに使える資産で、短期の支払いをすべてカバーできる状態が理想です。当座比率が100%を下回ると、「在庫に頼らなければ支払いができない」という状況にあることを意味し、注意が必要です。
流動比率・当座比率の使い分けと見るポイント
これまでに紹介した例の指標を並べてみましょう。
【流動比率】:150%=1,500万(流動資産) ÷ 1,000万(流動負債)
【当座比率】: 80%= 800万(当座資産) ÷ 1,000万(流動負債)
流動比率は高水準で安心感がありますが、当座比率は注意ゾーンです。
このギャップが意味するのは、「在庫頼みの安全性」です。
もし棚卸資産の回転が鈍い場合や価値が目減りしていると、支払い能力は大きく損なわれてしまいます。
ここで重要なのは、数値の見栄えだけで経営判断を下さないことです。
数字が示す背景を読み解く力が求められます。 ・売掛金の回収はスムーズか?
・売掛金の回収はスムーズか?
・在庫は必要量に収まっているか?
・実際に資金化できるのはどこまでか?
こうした問いを持つことで、数字は“判断材料”として初めて意味を持ちます。
会計は単なる記録ではなく、経営のナビゲーションツールだということを忘れてはなりません。
【まとめ】貸借対照表は企業の健康診断書
【流動比率】と【当座比率】は、貸借対照表から読み取れる“短期安全性”を測る基本指標です。
流動比率が高ければ良い、当座比率が低ければダメではなく、それぞれの「中身をどう読み解くか」が経営判断のカギになります。
特に中小企業においては、在庫が多くなりすぎていたり、売掛金の回収が遅れていたりすることで、気づかないうちに資金繰りが悪化するケースも少なくありません。
だからこそ、表面的な数値に安心せず、「その裏にある資産の質や資金の動きを定期的にチェックする姿勢」が重要です。
貸借対照表は、単なる過去の記録ではなく、未来の意思決定に活かせる“企業の健康診断書”です。
資産と負債のバランスを見極め、企業の持続的な成長を支えるためにも、指標の意味を正しく理解し、活用していきましょう。

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。
趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。