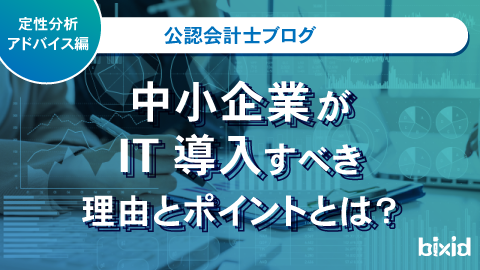DXとは何か?事例紹介と推進のポイントを解説
DXとは“デジタルトランスフォーメーション”の略であり、
「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という意味です。
なぜ今、DX化の推奨が盛んにおこなわれているのか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?
DXという概念はIT化と思っておられる方も多いですが、実は違います。
IT化というのは業務効率化を”目的“にデジタル化を進めましょうという意味合いで、
DXというのはデジタル化が目的ではなく、あくまで”手段”ということです。
今回は、DXとは何かを簡単にわかりやすくご説明した上で、DX化の事例についてもご紹介いたします。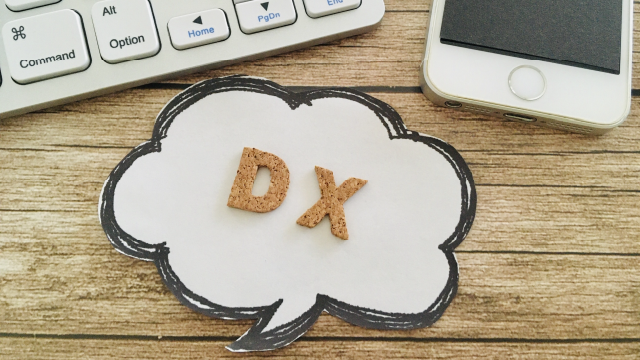
DXとは何か?
DXは、スウェーデンにあるウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年に提唱した概念です。経済産業省では、DXを以下のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
(参照:中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き)
わかりやすく言うと、「デジタル技術を活用して抜本的にビジネスモデルを変革すること」です。
DX化が推進されるようになったのは、2018年9月、経済産業省が発表した「DXレポート~IT システム『2025 年の崖』の克服と DX の本格的な展開~」の内容に、多くの関係者が衝撃を受けたことが要因といわれています。
そのレポートとは、 テクノロジーの進化に対応できる先端IT人材が不足していることを示し、また、これらを解決できない場合、DXが実現できないだけでなく、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失が発生する恐れがある、と言及しているものでした。
日本は、DX人材の不足やレガシーシステムを利用する企業が7割以上と、海外に比べて圧倒的に遅れをとっています。日本の国力低下を防ぐためには、DXを通じて企業の根本を変えていく必要があるのです。
DX化の事例
電通デジタルが2020年末に実施した調査では、コロナウイルス感染症の拡大によってDX推進を加速したと答えた企業は、実に50%に達していると報告されています。
しかし、いくら勢いが増しているとはいえ、DXによって具体的に何が実現できるのかが見えてこないと自社に導入するイメージがつきにくいですよね。
そこで、ここでは私達の身近な企業で実際にDX推進に成功している企業をご紹介いたします。
【新たな顧客体験を生み出したJapan Taxi(日本交通)】
タクシー会社としておなじみの日本交通。その情報部門からスピンオフしたJapan Taxiの例をご紹介します。 Japan Taxiでは、乗車場所を選択してボタンを押すだけで、すぐに周辺のタクシーを呼ぶことができる配車アプリを提供しています。このアプリにはWallet機能も付随しており、タクシー後部座席のタブレットに表示されるQRコードを読み取るだけで事前に支払いまで完了することができるサービスも利用できます。
Japan Taxiでは、乗車場所を選択してボタンを押すだけで、すぐに周辺のタクシーを呼ぶことができる配車アプリを提供しています。このアプリにはWallet機能も付随しており、タクシー後部座席のタブレットに表示されるQRコードを読み取るだけで事前に支払いまで完了することができるサービスも利用できます。
アプリの導入により、顧客側にとっては急いでいるときにスムーズにタクシーの手配や支払いができるという体験を、日本交通などの企業側にとっては現金管理や釣り銭確保の負担軽減などの価値を提供することができているといいます。
さらに先述したタブレットを活用した広告事業も新たな収入源として開始しており、タクシーを利用するビジネスマン向けの媒体としての売上も好調とのこと。こちらの事業は各車両から収集できるデータと組み合わせることができるため、さらなるビジネス展開にも期待が寄せられています。
こちらはまさに、DX推進によって新たなビジネスチャンスを見つけることに成功した例といえるでしょう。
【業務時間の短縮に成功した株式会社学研ロジスティクス】
物流事業を手掛けている株式会社学研ロジスティクスの事例をご紹介します。 こちらの企業では、かつて申込書や引き落とし用紙をすべて紙で管理していたことで、繁忙期には入力専用の人材を20名追加雇用する必要が生じていました。
こちらの企業では、かつて申込書や引き落とし用紙をすべて紙で管理していたことで、繁忙期には入力専用の人材を20名追加雇用する必要が生じていました。
この課題を解決するために彼らが導入したのが、手書きの文字を高精度で読み取ることができる「DX Suite」というサービスとRPA(Robotic Process Automation)を組み合わせたシステムです。
このシステムを導入することで、データの読み込みだけでなく、確認・修正といった作業の負担も軽減し、業務時間の削減につながったといいます。
こちらは、DXにより作業時間や人件費といったコストを削減することに成功したわかりやすい実例といえます。
DX化のポイント
実際に自社でDXを推進するために意識すべきポイントを3つに絞ってご説明いたします。
サービスが永続的に選ばれ続けるためには、このサイクルを回していけるかが課題になっていくといえるでしょう。
①目指すべき目的とそのための戦略
これは最も重要なポイントです。多くの企業がDXに取り組んでいるからといっても、自社の課題にあった目的と戦略がなければ、ただITに振り回されて終わる危険性もあります。
まずは、なぜDXに取り組むのか、どのような価値を生みたいのか、そのためにどのようなシステムにするのかなどをしっかり戦略として整えておく必要があるでしょう。
②組織内の風土や体制
DXは、これまでとは全く違うチャレンジをすることがベースとなっています。変化を嫌ったり、新しいものに拒否反応を起こしたりするような土壌では、中途半端な結末にとどまってしまう可能性もあります。各部署のキーマンや経営層も含めて、社内一体となってプロジェクトに取り組む姿勢を作ることも重要となります。
③DX推進による顧客体験を差別化し、そこから得られるデータも活用
DX推進によって選ばれるサービスになることで、そこからまた膨大なデータを得ることができます。このデータはサービスの改善だけではなく、新しいニーズやターゲットの分析、さらなる差別化などにも利用することが可能です。
まとめ
DX化は、IT化といった業務効率化の為のテクノロジー導入ではなく、経営方針やビジネスモデル、組織形態そのものを見つめ直す変革を指します。
DXを推進することで、新たなチャンスやターゲットを見つけ出したり、今の自社の課題を解決したりといった効果も期待できます。
テクノロジーについていけないことにより損失を被ることが無いように、まずは自社の課題を見つけ、対応策としてどのようにDXを導入していくのかを検討するところから始めてみませんか?