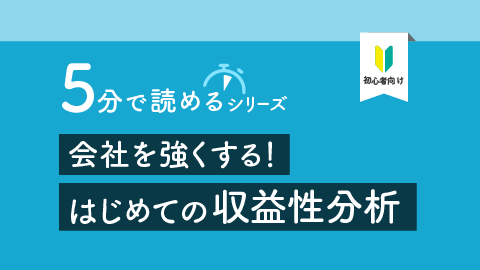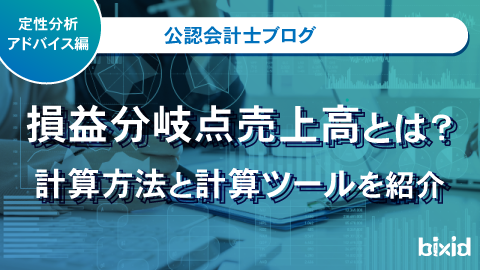財務分析とは?必要性を解説
こんにちは。YKプランニング代表取締役社長の岡本です。
今回のテーマはズバリ「財務分析」です。
財務分析と聞くと、一見、難しい概念に思えるかもしれません。
ところが実際には、私たちのビジネスが今どんな状況にあるのか、どんなチャンスや課題があるのかを探る、まるで探偵のような作業なのです。
特に、中小企業の経営者の方や会計事務所でがんばる若手スタッフの方にとって、これは数字を追うだけではない、もっと大きな価値を持ちます。
なぜならば、この財務分析を通じて、企業の現在地を正確に把握し、未来の方向性を見定めるための重要な手がかりを得られるためです。
財務分析とは具体的にどんなものなのでしょう?
どうして私たちにとって重要なのでしょうか?
どのようにしてそのメリットを最大限に活用できるのでしょうか?
今回のブログでは、これらの疑問を解き明かしていきます!
財務分析とは?
財務分析とは、簡単に言うと、会社の「健康診断」のようなものです。 医者が私たちの体調をチェックするように、財務分析は会社の財務状態を詳しく調べ上げます。これには、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書といった、企業のお金の流れを示す書類が使われます。
医者が私たちの体調をチェックするように、財務分析は会社の財務状態を詳しく調べ上げます。これには、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書といった、企業のお金の流れを示す書類が使われます。
この分析をおこなうことで、企業がお金をどのように稼ぎ、使っているのか、また資金の流れがスムーズかどうかを詳しく知ることができるのです。
なぜ財務分析が必要なのか?
財務分析は、数字の追跡だけではなく、企業の健全性を保ち、将来の成功に向けた戦略を練るうえで不可欠なプロセスです。この分析を通じて、中小企業の経営者や会計事務所の若手スタッフは、現在の経営状況を正確に理解し、未来への道筋を描くための具体的な行動計画を立てることができます。
また、単に数字を解釈するだけでなく、それらの数字が示す物語を読み解き、企業の強みを活かし、弱点を克服するための戦略を策定することを可能にします。
特に中小企業では、資源が限られているため、投資の優先順位を正確に設定し、限られた資源を最も効果的に活用することが成功の鍵となります。財務分析を通じて得られる洞察は、資金配分、コスト削減の機会、収益性の向上策など、企業の財務健全性を維持しつつ成長を促進するための重要な意思決定を支援します。
さらに、財務分析は外部ステークホルダーに対しても価値があります。投資家、貸し手(金融機関)、取引先などは、財務分析の結果を通じて企業の健全性や将来性の評価が可能となります。
したがって、財務分析のスキルを身につけ、定期的に分析を実施することは、信頼性の高い経営情報を外部に伝え、良好なビジネス関係を維持するためにも不可欠なのです。
財務分析の活用方法
財務分析の活用方法は以下の3つです。
①比較分析
過去のデータや他社との比較を通じて、自社の位置を把握します。
②傾向分析
数年間のデータを分析し、財務のトレンドを探ります。
③比率分析
様々な財務比率を用いて、会社の健全性やパフォーマンスを評価します。
財務分析は複雑に思えるかもしれませんが、基本的な理解と適切なツールの使用により、中小企業の経営者や会計事務所の若手スタッフでも効果的におこなうことができます。このプロセスを通じて、企業はより強固な財務基盤を築き、変化する市場環境の中で競争力を保持し続けることが可能になります。
財務分析4つの柱
これまでの説明で、財務分析が企業経営における「健康診断」としてどのように機能するか説明してきました。
これからは、より深く掘り下げて、財務分析を構成する4つの重要な柱
①収益性②安全性③資金力④効率性について詳しく見ていきます。
この4つの柱は、企業が現在どの位置にあるのか、そしてどこを目指すべきかを理解するうえで不可欠です。 ①収益性
①収益性
収益性は、企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示します。これは、売上高に対する純利益の割合や、投資された資本に対するリターンなど、さまざまな指標を用いて評価されます。収益性の分析を通じて、企業は市場での競争力や価値創造能力を把握し、収益性を高めるための戦略を練ることができます。
②安全性
安全性は、企業が負債やその他の財務上の義務をどれだけ安全に、かつ持続可能な方法で管理しているかを示します。これは負債比率や流動比率などの指標を用いて測定され、企業の財務安定性を評価します。高い安全性は、不確実な経済環境下でも企業が生き残り、成長するための基盤を提供します。
③資金力
資金力は、企業が必要な資金をどれだけ確保し、運用できるかに関する能力を指します。これは、キャッシュフロー分析や資金調達の選択肢を通じて評価され、企業の成長や投資計画の実行能力を示します。十分な資金力を持つことは、新たな機会を追求し、競争上の優位性を築くうえで欠かせません。
④効率性
効率性は、企業がその資源をどれだけ効果的に利用しているかを示します。これには、在庫回転率や売上高に対する従業員数など、さまざまな指標があります。高い効率性は、リソースを最大限に活用し、コストを最小限に抑えることを通じて、企業の全体的なパフォーマンスを向上させます。
これら4つの柱は、財務分析の基礎を形成し、中小企業の経営者や会計事務所の若手スタッフにとって、会社をより良く理解し、経営戦略を練るための重要なツールとなります。
次回からのブログでは、これらの要素についてさらに詳しく掘り下げていきますので、お楽しみに。

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。
趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。