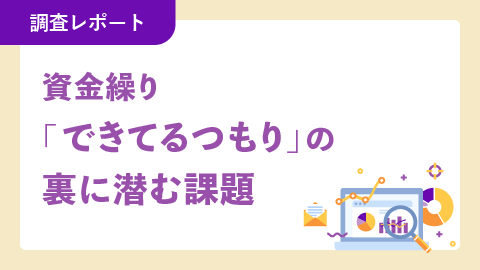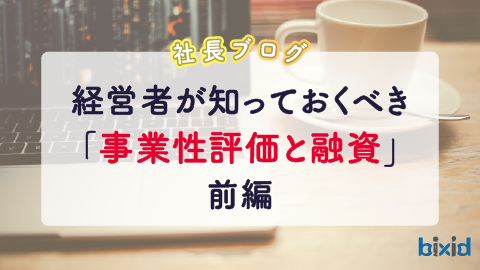【経営ウォッチ】ワークマン流の「しない経営」
作業服専門店として知られる「ワークマン」。
かつては建設現場の職人を中心とした専門業態でしたが、一般消費者からも高い支持を得るブランドへと進化しています。
2025年3月期の本決算によると、全店売上高は約1831億円に達し、経常利益率は13.6%と、業界でも高収益を維持しています。
原材料費の上昇や季節商品の需要変動など、環境変化の影響で収益を確保しづらい企業が多い中で、これほど高い利益率を維持できる企業はまれです。その背景には、現場主導の仕組みと自律的に動く組織文化があります。 今回の【経営ウォッチ】では、ワークマンの組織づくり・人材育成・経営改革の仕組みを紐解きながら、中小企業でも応用できるヒントを探っていきます。
今回の【経営ウォッチ】では、ワークマンの組織づくり・人材育成・経営改革の仕組みを紐解きながら、中小企業でも応用できるヒントを探っていきます。
“しない経営”に見るワークマンの哲学
ワークマンの急成長を支えるキーパーソンの一人が、専務取締役の土屋哲雄氏です。
商社で30年以上にわたり第一線を走ってきたのち、ワークマンへ転身。異業種からの視点を活かしながら、同社の組織改革を牽引してきました。
土屋氏が提唱するのが、「しない経営」という考え方です。
これは「頑張りすぎない」「ノルマを設けない」「過剰な管理をしない」「残業しない」「社内行事をしない」「無理に接客しない」といった、一般的な企業の“常識”とは逆を行く経営方針を指します。
一見すると消極的にも見えるこのスタイルこそが、ワークマンの競争力の源泉となっています。管理を減らすことで社員一人ひとりの自主性を引き出し、ノルマよりも顧客ニーズや現場改善に向き合う時間を増やす。「やらないことを決める」ことで、結果として生産性と創造性の両立が実現しました。
このアプローチが浸透したことで、ワークマンは短期的な売上目標に追われず、中長期のブランド成長に集中できる組織へと変化。「手を抜かずに、ムダを省く経営」を体現する企業となっています。
ファンがブランドを育てる ― 「アンバサダーマーケティング」の力
ワークマンの急成長を支えたもうひとつの柱が、「WORKMAN Plus」に代表される新業態の展開です。
土屋氏は入社後、従来の“作業服専門店”というイメージを超え、一般消費者にも親しまれるアウトドア・スポーツウェア市場へと活路を見出しました。これにより、同社は「職人のための店」から「すべての働く人・アクティブに生きる人の店」へと進化します。
この変革を後押ししたのが、「アンバサダーマーケティング」というユニークな手法でした。
ワークマンでは、もともと製品に強い愛着を持つユーザーを「アンバサダー」として選定し、実際に新素材や商品を提供。アンバサダーたちは登山、キャンプ、バイクなど、自らのフィールドで製品を体験・発信します。これにより、企業広告では届きにくいリアルな声がSNSや動画を通じて広まりました。
アンバサダーの投稿は、単なる宣伝ではなく、「ユーザー目線の信頼性」を生み出します。結果としてワークマンの商品は“安くて高機能”というイメージに加え、“使ってみたい・共感できる”というブランド価値を獲得。さらにアンバサダーの発信が注目されることで、彼ら自身のフォロワー増・収益向上にもつながるという、双方にとってWin-Winの関係を築いています。
この仕組みは、広告費を抑えながらブランド力を高める「共創型マーケティング」の成功例ともいえます。従来のように企業が一方的に情報を発信するのではなく、ファンやユーザーとともにブランドを育てる、これがワークマン流のマーケティング革新です。
現場を起点にした「データ経営」が支える進化
「しない経営」やアンバサダーマーケティングで新たな市場を切り拓いた土屋氏の改革を、より強固に支えたのが「データ経営」でした。 ただしワークマンのデータ経営は、数字を集めて管理することが目的ではありません。社員一人ひとりが、データを“自分の行動を変えるための道具”として使うことを重視しています。
ただしワークマンのデータ経営は、数字を集めて管理することが目的ではありません。社員一人ひとりが、データを“自分の行動を変えるための道具”として使うことを重視しています。
土屋氏が提唱するデータ経営は、単なる利益計算ではなく、「仮説を立て、実行し、結果を数字で検証する」というプロセス型の経営です。売上や在庫の数字を見て終わりではなく、「なぜその結果になったのか」「何を変えればより良くなるのか」を考える。その思考を全社員に浸透させるために、エクセルを使った実践的なデータ分析教育が全社でおこなわれました。
ここで重要なのは、“数字の裏側”を読み解く力です。
たとえば「この商品は売れなかった」という結果を前に、データだけを見て「人気がなかった」と結論づけるのは簡単です。
しかし「なぜ人気が出なかったのか」「売り場配置・価格設定・天候など、どんな要因があったのか」まで踏み込むには、現場感覚が欠かせません。
また、ワークマンでは、分析に強みを持つ社員が、専門部署でより深くデータに関わることができる体制も整えました。
店舗運営や商品管理など、日々の業務を肌で感じている社員が分析に関わることで、データに現れない“現場の実感”を読み取ることができるようになったのです。
結果として、数字に基づきながらも現場の判断を尊重する、実践的なデータ活用が可能になりました。
まとめ
「WORKMAN Plus」で一般消費者への展開を成功させたワークマンは、その後、日常をより快適にするブランドづくりへと歩みを進めました。
レディースラインの強化や新たな店舗展開を進める中で、近年ではブランド名を「Workman Colors」へと改称し、より多様な顧客層に寄り添う姿勢を打ち出しています。
こうした動きは、単なるブランド名の変更にとどまらず、これまで培ってきた経営哲学と現場の知見を土台に、次の成長段階へと進化していることを示しています。
その成長の背景には、“頑張らない・ノルマを課さない”という「しない経営」と、社員全員がデータを活用して仮説・実行・検証を繰り返す「データ経営」がありました。経営者が「何をすべきか」を定めるのではなく、「何をしないか」を選び取り、現場の声と数値を融合させたことで、普通の延長ではたどり着けなかった成長曲線を描いたのです。