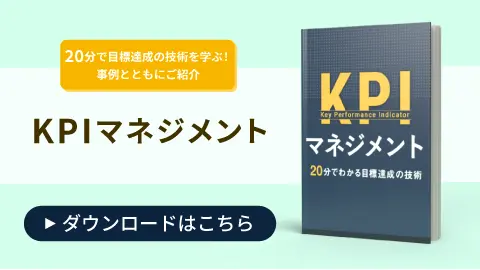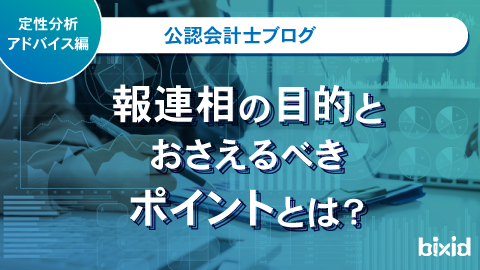管理職が知っておきたい「マネジメントとリーダーシップの違い」
「経営者なんだから、リーダーシップを発揮しないといけない」「マネジメント力がないと組織は回らない」
そんな言葉を耳にすること、ありませんか?
けれど実際に現場に立つと、リーダーシップとマネジメントの線引きはあいまいで、「どちらを意識すればいいのか」迷う場面も少なくないかと思います。
今回は、あらためてその違いと関係性を整理しながら、これからの組織づくりのヒントを一緒に考えてみたいと思います。
リーダーシップとは「人を動かす力」
リーダーシップと聞くと、「先頭に立って引っ張る」「強いカリスマ性を持つ人」というイメージを持たれる方もいるかもしれません。ただ、現代のリーダーシップはそうした“強さ”とは少し違ってきています。 リーダーシップについては、かの有名なドラッカー博士や「7つの習慣」の著者・コヴィー博士など、多くの識者がさまざまな方向から定義しています。 なかでも、彼らの定義に共通しているのは以下の3点です。
リーダーシップについては、かの有名なドラッカー博士や「7つの習慣」の著者・コヴィー博士など、多くの識者がさまざまな方向から定義しています。 なかでも、彼らの定義に共通しているのは以下の3点です。
・組織内で定められた目的を達成するためのチームの方向性を定める
・目的を達成するためにチームとしての集団活動を維持する
・目的達成のための課題を積極的に解消していく
つまり、リーダーシップとは「人が自然とついていきたくなるような影響力」であり、「ビジョンや価値観を示して方向性をつくる力」です。
たとえば、困難な状況で「大丈夫、一緒に乗り越えよう」と声をかける、意味を語り、チームのやる気を引き出す、自分が率先して挑戦する姿を見せるといった日常の中にこそ、リーダーシップは現れます。
マネジメントとは「仕組みを回す力」
一方のマネジメントは、もっと現実的な「業務運営」や「計画遂行」に関わるものです。
・目標達成のための中期的、長期的な戦略を立てて進捗を管理する
・メンバーの特性とスキルを把握し、適切に配置・役割分担する
・規則や秩序を遵守する意識をもち、問題が起きた時に原因を特定し、再発を防ぐ
といった「成果を出すための再現性のあるプロセス作り」がマネジメントの役割です。
どちらが良い・悪いではなく、組織運営にはどちらも欠かせないピースです。
リーダーシップとマネジメントの違い
よく「リーダータイプ」と「マネージャータイプ」といった分け方をされることもありますが、実際にはその両方の役割を経営者自身が担っていることも多いと思います。
次の2つのポイントから具体的に考察してみると、その違いが明確になります。
1.役割
リーダーシップの最も重要な役割は「ビジョンを示す」ことです。
この役割を果たすためには、長期的な視野や未来的な思考を持っていることが求められます。リーダーがより明確にビジョンを示していくことで、組織内で目指すものが一致し、活動を維持していくことが可能となるのです。
一方マネジメントで重視される役割は「目標の達成」です。
こちらはリーダーシップと比べてより現実的かつ実務的であることが特徴であり、どのように目的を達成していくのかという戦略だけでなく、メンバーの現状把握、モチベーション管理、トラブル時の対応などの部分もマネジメントの役割となります。
2.人間性
リーダーシップに必要となるのは「誠実さ」「人望」だと言われています。
リーダーになる人物は企業や組織のビジョンを示し、同じ方向へメンバーを導いていかなければなりません。 様々な考えを持つ人が集まったチームを率いていく上で大切なのが、「信頼関係」です。 自分自身の言動を一致させるなどの誠実さや人間的な魅力が、チームを率いていく立場としては必要不可欠となります。
反対に、マネジメントを担う人間に必要となるのは「現実的な視点」です。
リーダーが未来視点でビジョンを示す一方で、マネージャーは現実的な視点からそれを見極め、落とし込んでいく必要があります。 目的を確実に達成するという役割を果たすためにも、現状を冷静に分析し、感情に左右されることなく判断を下すことができるという素質がマネジメントには重要となるのです。
そして、重要なのは「場面によって使い分ける」ということです。
たとえば、
・新規事業の立ち上げ時は、熱量や方向性を示すリーダーシップが重要。
・会社が安定期に入ったら、品質を維持し、効率化を図るマネジメントが求められる。
こうして組織のフェーズに応じて、リーダーシップとマネジメントのバランスを意識していくと、より経営のハンドリングがしやすくなるかもしれません。
サーバントリーダーという考え方
最近注目されている「サーバントリーダー」という概念もご紹介したいと思います。
サーバント(=奉仕者)という言葉の通り、リーダーが「支配する人」ではなく「チームを支えること」を主な役割とする新しいタイプのリーダー像です。この概念は、1969年にアメリカのロバート・グリーンリーフ博士によって提唱されました。
・部下の話に耳を傾ける
・必要なリソースを整え、動きやすくする
・メンバーの成長や自立を促す
といった関わり方で、心理的安全性を高めることができます。
近年、企業のグローバル化や人々の価値観の多様化が進み、従来の支配型リーダーの手法は時代にそぐわないものとなりつつあります。そんな中、今から50年以上も前に提唱されたサーバントリーダーが、現代社会に適した多彩な人材を上手く束ねることができるリーダー像として、再び注目を集めているのです。
これは特に、専門知識を活かす職種や自律性の高いチームにおいて、とても効果的なスタイルです。サーバントリーダーはメンバーの意見を尊重し、信頼関係を築くことでチームの成果向上や人材の成長を促します。こうした姿勢が好循環を生み、上司・部下が互いに信頼し合う組織づくりに繋がります。
管理職としての関わり方を見直してみる
「もっとしっかりマネジメントしなきゃ」「チームが思うように動かない」と感じている方もいるかもしれません。
そんなときは、あえて一歩引いて「管理すること」よりも「支えること」に視点を置いてみると、新しい気づきがあるかもしれません。
たとえば、チームメンバーが何に悩んでいるのか聞いてみる、なぜその仕事をやるのか、目的を共有する、感謝やねぎらいの言葉をかけてみるなど、こうした小さな行動が、リーダーとしての信頼を積み重ね、自然とチームが動き出すきっかけになります。
両方を使い分けて組織を導く
リーダーシップとマネジメントは、どちらか一方だけでは成り立たないものです。
組織の方向性を示しながら、現場の運営もしっかり支える、そんな「両輪」が経営者には求められます。
とはいえ、完璧を目指す必要はありません。日々の中で、自分の強みやスタイルに合ったバランスを見つけながら、少しずつアップデートしていければいいのではないでしょうか。
あなた自身のリーダーシップとマネジメントのかたちは、これから作っていけるものです。