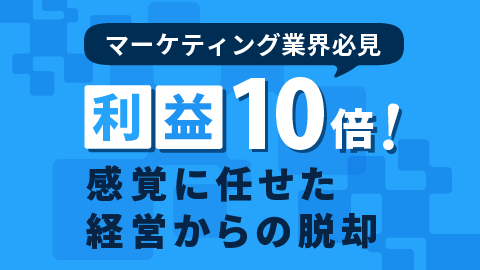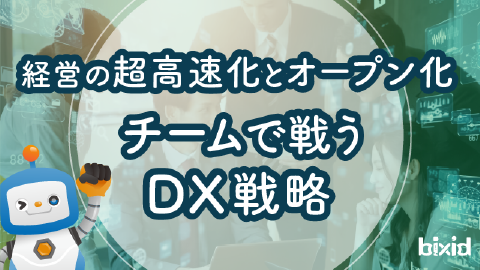これからの中小企業に必要な「ESG」
「ESG」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。この言葉は、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の頭文字を取ったものです。
ではこの「ESG」に企業が取り組むべき理由は何なのでしょうか。この記事ではESGの基本と注目される理由、そしてSDGsとの違いを紹介します。
ESGとは
ESGは、企業の持続性を判断する1つの基準として捉えられています。
かつて企業の持続可能性は財務状況による判断が多かったのですが、時代ともに環境問題・社会問題への取り組みによる判断が増えてきました。投資の主流もESG投資になってきたこともあり、企業が取り組むテーマとしても注目されるようになっています。
ESGそれぞれの具体的な例は、以下のようなものが挙げられます。
Environment(環境)
脱炭素への取り組み、再生可能エネルギーの利用、サーキュラーエコノミーへの取り組みなど
Social(社会)
ダイバーシティ、ワークライフバランス、働き方改革、地域社会への貢献など
Governance(企業統治)
法令順守、コンプライアンスの遵守、リスク管理のための情報開示など
これらの要素をどれだけ企業が叶えられているかが、企業の成長を見据える重要なものさしとなってきているのです。
なぜ今ESGが注目されるのか
では、なぜ今、ESGが注目されているのでしょうか。
近年、社会的問題が顕在化されることに伴い、企業が各問題にどのように貢献しているかが注目されるようになりました。
特に2006年、国連が「責任投資原則」を発表して以降、その動きは強まってきています。国連は、この「責任投資原則」の中で、機関投資家が投資をする際にはESGを意識するよう提唱しています。日本では2015年に世界最大級の投資運用機関である「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)」が署名し、 ESGインデックスを導入しました。
当初、この原則への賛同署名は数十社ほどでしたが、2018年には署名の数は1900社ほどになり、ESGは世界規模で存在感を増しました。
以上の背景から、企業は自社のESGの取り組みを投資家にアピールすることが必要となり、ESGが注目されるようになったのです。
ESGとSDGsの違い
ESGと混同されやすい概念として、SDGsがあります。
SDGsは、2015年9月の国連総会で示された、2030年に向けた国際的な開発目標です。これは、企業はもちろん、「国・自治体・非営利団体も含めた組織」が一丸となって取り組むべき目標となっています。
対してESGは、投資家をはじめとしたステークホルダーを意識した、「企業」が取り組む施策です。ESGの施策に積極的に取り組むことにより、企業の長期的な発展を見込むことができるという考え方が元になっています。
目標となるゴールは似ていますが、取り組む主体や意識する相手によってSDGsとESGは異なります。企業のESGの取り組みが、結果としてSDGsに繋がることは大いにあり得るので、整理して理解しておくと良いでしょう。
まとめ
ESGはステークホルダーへの配慮であると同時に、企業が長期的に持続して活動するには欠かせない取り組みです。積極的に取り組むことで、注目が集まったり好感度が上がったりといった良い影響が期待できます。
ただし、ESGの取り組みが上手く流れに乗るまでは時間がかかります。できることから少しずつ、長い目で考えながら取り組んでいきましょう。