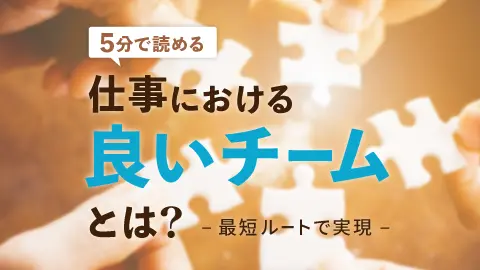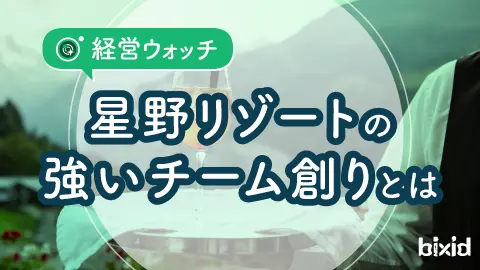離職率28%脱却の舞台裏!サイボウズ改革(前編)
「企業文化なんて、雰囲気の話でしょ?」
そう思われがちですが、実は企業文化は、離職率や業績にも影響する“経営資源”のひとつです。
制度やシステムをただ整えるだけでは、社員が安心して働ける職場は実現できません。文化という「空気」こそが、人の行動やチームワークを育て、企業の成果に結びついていくのです。
本記事では、離職率28%という危機から脱却し、先進的な働き方を実現したサイボウズの事例を通じて、「企業文化の力」に迫ります。
離職率28%の危機と、昭和的な働き方の限界
1997年に創業したサイボウズは、当初は順調に成長を続けていました。
しかし、2005年ごろ、大きな壁に直面します。社員の離職率は28%に達し、4人に1人が毎年やめていくという深刻な状況に陥っていたのです。採用しては去っていくという負の循環が起こっていました。
当時の職場環境は、次のような非合理的なルールや慣習が残っていました。
・副業は禁止
・出張は日帰り、タクシーはNG
・昼休みにはみんなでラジオ体操
・突然、徹夜しなくては終わらない業務が発生
今でこそ「昭和的」と言われそうなこの働き方も、当時は「規律に従うのが社会人」「我慢は美徳」という価値観のもと、ある程度受け入れられていました。社員の多くも「ベンチャー企業とはこういうものだ」と考えていたようです。
一方で、こうしたルールや空気感が「ここで働き続けたい」と思わせる環境になかったのも事実です。社員の離職が相次ぐ中で、サイボウズは大きな転換点を迎えることになります。
「100人いれば100通りの働き方」に気づくまで
離職率が28%に達していた2005年、サイボウズは重大な転機を迎えます。
このタイミングで、青野慶久氏が代表取締役社長に就任しました。
採用してもすぐに退職者が出る状態は、経営にも深刻な影響を与えていました。
人材採用にかけたコストや時間が組織に定着せず、ノウハウも蓄積されない。これは経営効率の低下だけでなく、会社の成長力そのものを損なう問題でした。
そこで、青野氏は「社員の福利厚生のため」というただの綺麗ごとではなく、「成果を出せる組織をつくること」を目的に社内改革に乗り出します。
まず取り組んだのは、社員の退職理由の徹底的なヒアリングでした。
退職理由は、家庭の事情や労働時間、キャリア希望、ライフスタイルなど、一人ひとり異なっていました。そこで青野氏は気づきます。
「100人いれば、100通りの働き方がある。」 つまり、画一的なルールでは、個々の事情や価値観に対応できないということです。
つまり、画一的なルールでは、個々の事情や価値観に対応できないということです。
誰もが同じ働き方をするのではなく、それぞれに合った働き方を選べるようにすれば、社員は辞めずに、長く活躍できる。
この気づきが、サイボウズの企業改革を大きく動かす原動力となりました。
離職率を改善した“サイボウズ式メソッド”とは
サイボウズ社内で独自に進められたマネジメント手法「サイボウズ式メソッド」。
この考え方は、アドラー心理学の「目的論」と非常によく似ています。
目的論とは
・人は「過去」ではなく「目的」によって行動する。
・今の行動は、「未来にどうありたいか」という理想によって決まる。
この考え方は、社員の離職にも当てはまります。
たとえば「もっと自由な働き方をしたい」「子育てと両立したい」など、退職の理由は過去の不満ではなく、“未来の理想を実現するため”です。
であれば、その理想が叶う環境を整えれば、社員が辞める理由はなくなります。
理想を叶える制度づくりへ
サイボウズは、「社員の理想を実現できる職場」を目指して、次々と制度改革を進めました。
・週3勤務や副業OK
・育休は最長6年
・勤務時間・場所は柔軟に選択可能
こうした制度の根底にあるのは、「個人の事情に合わせて柔軟に働ける環境が、結果的に組織の成果につながる」という信念です。
社員に「サイボウズだからこそ、自分の理想を実現できる」と感じてもらえること。
それこそが、離職率の改善につながったのです。
青野社長の哲学が導いた、サイボウズの企業改革
「育休最長6年」「副業OK」など、これまでにない柔軟な制度を次々と導入したサイボウズ。中でも、働くママへの手厚い支援に対し、当初は「なぜママだけをサポートするのか」という声があがることもありました。 しかし、そんな意見に対して青野氏は、「彼女たちはそうしないと働けないだけであって、自分で働き方をリクエストしてくれれば会社は実現するから、自分以外の働き方に文句を言うべきではない。」と語りました。
しかし、そんな意見に対して青野氏は、「彼女たちはそうしないと働けないだけであって、自分で働き方をリクエストしてくれれば会社は実現するから、自分以外の働き方に文句を言うべきではない。」と語りました。
この考え方は、従来の「全員に同じルールを」という平等重視の発想とは異なります。青野氏が目指したのは、それぞれの事情や環境に応じた“結果の公平性”です。
・誰もが違う事情を抱えている
・働き方の理想も、人によって違う
・だからこそ、それぞれに合った形で働けるようにする
こうした哲学が背景にあったからこそ、サイボウズは「100人いれば100通りの働き方」を実現するための制度改革を本気で推進し、社員一人ひとりの理想に寄り添う企業へと変わっていったのです。
まとめ
こうして、離職率28%という危機に直面したサイボウズは、青野氏の哲学や「サイボウズ式メソッド」により、制度改革を進めていきました。
一人ひとりの理想に寄り添い、社員が自分らしく働ける環境を整えるという思想が、組織の再生を支えたのです。
しかし、企業の成長を支えたのは、制度そのものだけではありません。
制度が現場で「文化」として根づき、社員の行動や意識を変えていったことも、また重要なポイントでした。
後編では、サイボウズがどのように「文化」を育み、それが組織にどんな変化をもたらしたのかを掘り下げていきます。
「働きやすさの本質」とは何か?その答えを、文化の視点から探っていきましょう。