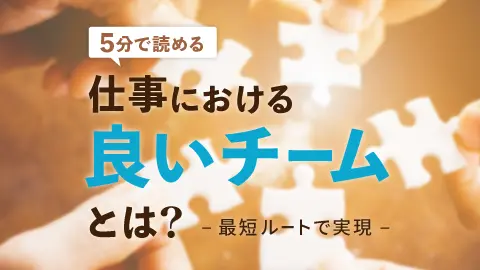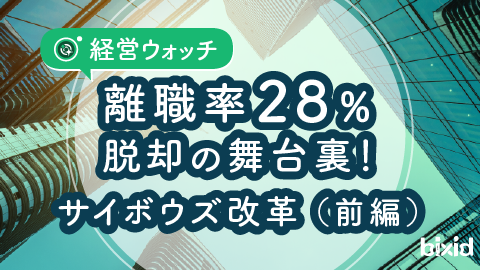離職率28%脱却の舞台裏!サイボウズ改革(後編)
サイボウズはかつて、離職率28%という深刻な人材流出に直面していました。
その背景には、「もっと自分らしく働きたい」「家庭や人生と両立したい」といった、社員一人ひとりが抱える“理想の働き方”の不一致がありました。
そこで同社は、「理想が実現できる職場であれば、人は辞めない」という発想に転換。
「100人いれば100通りの働き方」をキーワードに、週3勤務・時短勤務・副業OK・リモートワーク自由など、多様な働き方を支える制度改革を本格的に進めていきます。
しかし、制度を導入しただけでは定着率は改善しないことに気づきます。
後編では、リモートワークという切り口から、サイボウズがどのように制度を文化として根づかせ、「働きやすい職場」へと進化していったのか、その本質に迫ります。
社員の「幸福度」を高めるリモートワーク
総務省実施の令和3年通信利用動向調査によると、日本におけるリモートワークの普及率は、コロナ禍を契機に2019年の20.2%から2021年には50%超へと拡大しました。
参考:令和3年通信利用動向調査
一見すると、柔軟な働き方が広がったようにも見えます。しかし、こんな報道を目にしたことはないでしょうか。
台風や積雪によって交通機関が麻痺した朝、駅には長蛇の列。多くのビジネスパーソンが出社を前提とした生活の中で混乱に巻き込まれている様子です。
「明日は台風直撃の恐れ」とニュースが報じられても、多くの人は翌日の出社に備え、天気とインフラの動向に気を揉む。もはや、自然災害のたびに繰り返される“おなじみの風景”となっています。
「電車が止まったらどうしよう」「帰れなくなったら」など。
そんな不安を抱えながらも、出社しなければ仕事が回らないという環境は、心身に大きな負担を与えます。どれだけ社内コミュニケーションが円滑で、心理的安全性が保たれた環境でも、働く場所に縛られた状況は、本当に“働きやすい”職場と言えるのでしょうか?
こうした課題に対し、サイボウズは早くから「場所にとらわれない働き方」の実現に取り組んできました。
2010年、社員に対し「在宅勤務に対してどう思うか?」という意見収集をおこない、その声をもとに、同年8月からリモートワーク制度の試験導入を開始しました。
リモートワーク導入後の課題から見えた“働きやすさの本質”
いまや「リモートワーク先進企業」として知られるサイボウズですが、導入当初からすべてが順調だったわけではありません。 2010年に試験導入された当時、在宅勤務をする際の申請は以下の流れとなっていました。
2010年に試験導入された当時、在宅勤務をする際の申請は以下の流れとなっていました。
1.実施の前日までに申請(勤務場所、勤務時間)
2.上長承認
3.在宅勤務の実施
4.勤務終了後、勤務時間と業務内容(作成資料など含む)を報告
5.上司評価
一見すると、必要な管理プロセスにも思えます。しかし、実際に利用した社員からは、こんな声があがったのです。
「業務終了後の報告がとてもストレスだった」
「ちゃんと報告しないと“サボっている”と思われそうで、報告書の作成に必要以上の時間をかけていた」
つまり、「サボっていないことを証明しなければならない」という不安が、働きやすさを損ねていたのです。この気づきをもとに、ルールと信頼関係のバランスを見直すことにしました。具体的には、「この働き方はチームの生産性を高めているか?」という視点で上司が判断し、懸念がある場合は本人にフィードバック。改善が見られなければ在宅勤務の制限をおこなう、という信頼ベースの運用にシフトしました。
信頼があるからこそ、社員は主体的に行動し、周囲の期待に応えようとする。
一方で、疑いや管理主義によって成り立つ制度では、人は本来の力を発揮できません。“制度を活かすのは信頼と対話である”これこそが、サイボウズが辿り着いた「働きやすさの本質」だったのです。
その後、2011年の東日本大震災をきっかけにリモートワーク制度は加速し、現在では場所・時間ともに自由な「ウルトラワーク」が導入されています。
制度を活かす“文化”──サイボウズの実践
「100人いれば100通りの働き方」を本気で実現しようとすれば、制度の設計以上に重要なのが、社員一人ひとりが制度を“自分ごと”として捉える文化的な下地です。
サイボウズでは、制度が単なるルールに留まらず、社員に根づく文化となるよう、次のような取り組みをおこなっています。
1.仕事Bar“一緒につくる制度”の文化を育む場
「仕事Bar」は、飲食を通じて業務上のコミュニケーションの質と量を高めることを目的とした制度です。カジュアルな雰囲気の中、真面目に仕事の話をする「場(Bar)」に対し、飲食費が会社から支援されます。
この取り組みは、2018年に発表された「新・働き方宣言制度」の導入に先立ち、人事主導でスタート。のべ80名の社員が参加し、制度の内容やあり方について活発な議論がおこなわれました。これにより、制度が「与えられるもの」ではなく「一緒につくるもの」として浸透していきました。
2.市場価値を取り入れた評価制度 自律と納得感を促す仕組み
一般的な年功序列での給与体制は、自分の市場価値や仕事の意味を深く考えずとも安定した報酬を得られます。
しかしその反面、「働くことに自分の人生をどこまで重ねるべきなのか」という疑問や、成長の実感を得にくいという課題も生じます。
サイボウズでは、こうした背景をふまえ、社員の市場価値をベースに給与を決定する制度を導入しました。
この「市場価値ベースの給与制度」では、一人ひとりが自分の働き方や価値を自覚し、「なぜこの給与なのか」を自ら説明・納得できることを重視しています。
これは単に給与を自由に決められるという話ではなく、「自分で選んだ働き方の結果として、この報酬である」という自己責任と納得感の両立を意味します。働き方が多様化する中で、社員に自律と対話を促す仕組みとなっています。 こうした“自分で考え、自分で選ぶ”という文化を醸成することで、制度は「使うか・使わないか」の枠を超え、自分ごととして活用されるようになります。
こうした“自分で考え、自分で選ぶ”という文化を醸成することで、制度は「使うか・使わないか」の枠を超え、自分ごととして活用されるようになります。
形ではなく空気として制度を根づかせる。
それが、サイボウズが考える「働きやすさ」の本質を支える企業文化なのです。
制度と文化の両輪がもたらした離職率28%からの脱却
こうした制度改革と文化づくりの両輪によって、サイボウズの離職率は大幅に改善しました。
かつて28%を超えていた離職率は、2020年代には一桁台をキープ。2023年時点でも離職率は約5%という数字が公表されています。
また、Great Place to Workによる「働きがいのある会社ランキング」調査にも毎年ランクインしており、企業イメージの向上にもつながっています。
社員それぞれの働き方を受け入れる風土。
情報が開かれた風通しのよい社内環境。
対話を通して育つ信頼関係。
こうした「文化」は数値化しづらく、目に見えにくいものかもしれません。
しかし、その成果は離職率の改善という形で確かに表れています。
制度はあくまで“道具”であり、それを活かすのは人と文化。
働き方改革が進む今、サイボウズの取り組みは「働きやすさの本質」を考えるうえで、多くの企業にとってこれからを生き抜く指針となる実例と言えるのではないでしょうか。