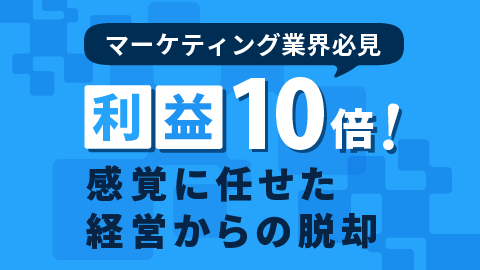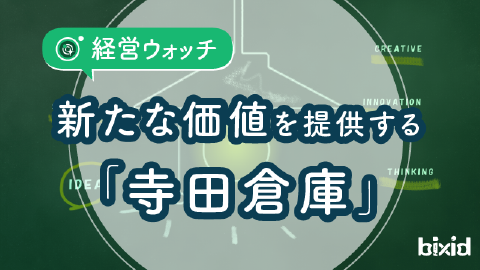【経営ウォッチ】バルミューダの芸術経営とは
SNS映えする見た目もお洒落な家電製品を多く発表していることで注目度の高いバルミューダ。長引くコロナ禍でお家時間を充実させたいと願う消費者に、同社の看板商品であるトースターがよく売れたのは記憶に新しいのではないでしょうか。
バルミューダは、企業としての歴史はさほど長くありませんが、消費者のみならず大手企業からも注目される存在です。今回の【経営ウォッチ】では、そんなバルミューダの「芸術経営」について見ていきます。
大手企業も一目置くバルミューダ
2003年に創業し、2020年に東証マザーズへ上場したバルミューダ。勢いはあるものの、売上高から見れば大手家電メーカーの方がまだまだ圧倒的です。
しかし、そんなバルミューダをお手本にしようと、その動向に注目する大手企業が実は数多く存在しています。バルミューダが注目されているのは一体なぜなのでしょうか。
バルミューダの強みとして挙げられる1つ目のポイントは、自社工場を持たず、中国や台湾、国内の工場に製造委託する「水平分業体制」を敷いていることです。これによって、自社では企画開発と販売に注力することが可能となり、営業利益率を高めることができています。
2つ目のポイントは、すでに成熟しきった市場で、相場にとらわれない高単価で製品を販売していることです。例えば、同社の看板商品である「バルミューダ・ザ・トースター」は2万5850円に価格設定されており、一般的なトースターの価格の4倍強の高単価で販売されています。
さらに、1つの「バルミューダ・ザ・〇〇」と名付けられる商品に対して型は1つだけで、価格のバラエティーはありません。一度発売開始した商品は、5年、10年と1つの型だけを発売し続け、定価販売が基本です。
商品の入れ替えを行うことで型落ち品が生まれ価格競争が起こる通常の家電とは全く異なる姿勢ですが、そのことを逆手に取り「一つの商品に創意工夫を重ねている」と消費者に自信を持ってアピールしているのです。
管理体制の課題と向き合う
大手企業にも注目され快進撃を遂げているバルミューダですが、品質管理という課題も存在します。
同社では2017年、18年、19年と連続で製品のリコールを発表しており、トースターのリコールをした2018年には自主回収と無償交換により12月の純利益が前年同期比95.7%減にまで落ち込んでしまいました。
このような経験から、品質面やコスト面の管理体制を強化することがバルミューダの課題とされており、上場を考え始めた当初の最大の目的は、会社の品質管理能力を強化することだったといいます。
初期には社長のこのような製品を作りたい、というパワーのままに製品を開発していくのがバルミューダのスタイルでした。しかし複数回のリコールを経験したバルミューダは、品質管理の課題と向き合うことを決め、開発の工程を細かな段階に分類し、各段階に達成目標を設けることによって組織力をあげることに注力します。その結果、上場会社にふさわしい管理能力を手に入れることができたのです。
まとめ
安価な家電製品が数多く出回る中、高年収の男性顧客をメインに高級家電を提供し続けるバルミューダ。大手既存企業からも注目を浴びる同社の強みは、「芸術経営」と自社の管理課題にしっかりと向き合う力でした。
上場後、企業スケールを大きくすることで更に飛躍しようと動き出しているバルミューダの今後から目が離せません。