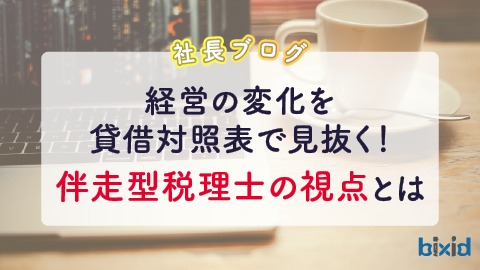経営改善に役立つ“会計のセカンドオピニオン”
こんにちは、YKプランニング代表取締役社長の岡本です。
先月のブログでは、「縦断的分析」というテーマで、“数字の変化”に注目して、会社の体質を見直すという視点をご紹介しました。
今回はさらに掘り下げて「他社と比べて、自社を客観的に見る」ことの大切さをお伝えします。
この記事を通じて、“数字の見方”を少しアップデートしていただけたら幸いです。
「経営の相談相手」はいますか?
多くの中小企業には顧問税理士がついています。毎月の試算表の作成や決算・申告業務、節税のアドバイスなど、日々の安心を支えてくれる大切な存在です。
しかし、それだけで経営者の意思決定が十分に支えられているかというと、答えはNOです。実際に、「数字は出してもらっているが、活用方法がわからない」「今後の打ち手について、数字をもとに相談できない」といった声を、私たちは多くの経営者から聞いています。税理士は“過去”をまとめるプロフェッショナルですが、“未来”を見通して提案してくれる存在かというと、それはまた別の専門性です。
経営の羅針盤として、数字をもとに一緒に未来を考えてくれるパートナー。それが、今の中小企業に必要とされている存在です。
“会計のセカンドオピニオン”という選択肢
経営にもセカンドオピニオンが必要です。これは、いまの顧問税理士を否定するものではありません。むしろ、税務という専門性をもったファーストオピニオンがあるからこそ、その役割と別の視点で企業を支援する存在として、セカンドオピニオンが意味を持つのです。
このセカンドオピニオンの役割を担えるのが、管理会計の視点を持った会計人です。
たとえば、同じ決算書でも、税務的に問題があるかどうかではなく、「この財務状態で新たな設備投資に踏み切るのは妥当か?」「資金ショートのリスクはないか?」といったように、より実践的な視点で企業の“経営の意思決定”をサポートできる為です。医療と同じように、「違和感がある」「判断に迷いがある」といった際に、別の専門家に相談することが経営にも必要です。
セカンドオピニオンという考え方は、今後ますます中小企業経営において重要になってくるでしょう。
他社と比べる、という視点
ここからは、視点を外に広げて、「他の会社と比べて、今の自社を知る」ということにフォーカスしていきます。
この“比較する”という行為は、非常にシンプルですが、非常に強力な気づきをもたらします。
たとえば、自社の自己資本比率が40%と聞けば、何となく健全に思えるかもしれません。しかし、同業他社の平均が60~70%だったとしたら、話は変わってきます。また、借入金が多いと感じていても、売上に対する比率(月商倍率)で見たときに、他社よりも突出して高ければ、そこには見直すべき構造的な課題がある可能性があります。
他社比較は、自社の数字に“相対的な意味”を与えます。数字そのものではなく、「周りと比べてどうか?」という視点をもつことで、はじめて見えてくる経営の課題や強みがあります。
黙っていても誰も教えてくれない「異常値」
実際に、私たちが支援した企業でも、比較によって初めて気づきを得た事例があります。
ある製造業の社長は、決算書を見て「黒字だし、借入も返しているから大丈夫」と思っていました。しかし、私たちが他社データと並べて見せたところ、以下のような差異が見つかりました。
① 借入金が売上の6か月分(他社平均は3か月)
② 固定資産比率が業界平均の1.5倍
③ 当座比率が60%以下で、支払い余力が低い状態
この数字を見た社長は、「そういえば資金繰りがずっときつかった」と呟きました。そこで初めて、銀行とのリスケジュールや固定資産の売却検討、資金繰り表の再作成といった具体的なアクションが始まりました。
異常値は、時には他社と比べなければ気づけません。誰かが教えてくれるわけではないのです。そこに寄り添い、数字の“異変”を一緒に言語化してくれる存在が、セカンドオピニオンなのです。
顧問税理士+もう一人の相談相手
誤解のないようにお伝えしておきたいのは、私たちは税理士を否定したいわけではありません。税理士は、税務のプロとして企業にとって欠かせない存在です。
しかし、経営とは税務だけでは語れません。これからの経営には、「過去をまとめる人」だけでなく、「未来を見通す人」が必要です。そして、その未来の方向性を、数字を通じて一緒に描いてくれる人。それが、会計のセカンドオピニオンです。
数字をもとに、「この設備投資はいつが適切か?」「手元資金はいくらあれば安心か?」といった経営の意思決定を一緒に考えてくれる。そんな“数字の伴走者”が、今の中小企業経営には求められているのではないでしょうか。
最後に
「数字について、誰とも深く話せていない」
そんな方こそ、セカンドオピニオンという新しい相談先を持っていただけたらと思います。そして、まだ先月のブログをご覧になっていない方は、「自社の変化に気づく」という視点からも、ぜひ一度目を通していただけると幸いです。

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。
趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。