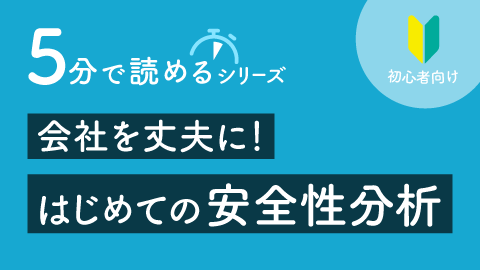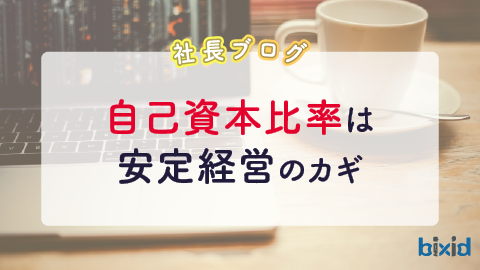経営の変化を貸借対照表で見抜く!伴走型税理士の視点とは
こんにちは、YKプランニング代表取締役社長の岡本です。
会社の成長を加速させるために税理士との連携は重要です。経営の意思決定を支えてくれる伴走者として、税理士と良い関係を構築したいと考える経営者の方は多いのではないでしょうか。
そこで、ポイントとなるのがBS(=貸借対照表)です。
PL(=損益計算書)だけでなく、BS(=貸借対照表)をどう見るか、この違いこそが、「いい税理士」と「そうでない税理士」を判断する分かれ道になるかもしれません。
会社を経営するうえでPLとBSは「過去の行動を記録した、経営の“足あと”」です。この両方が揃って初めて、未来に向けての正しい意思決定ができるようになります。
今回は「数字で語れる税理士」と一緒に、未来をつくっていける経営者が増えることを願って、「縦断的分析=自社の変化を読み取る視点」をご紹介していきます。
PL中心の税理士では頼れない?貸借対照表の重要性
BSは、企業の財務状況を瞬間的に切り取った“経営のスナップ写真”です。
資産・負債・自己資本の三要素から、「何にお金を使い、どうやって集めたのか」が見えるこの財務諸表は、本来、経営の土台を支えるものです。 しかし、多くの中小企業では、いまだに税理士からの説明が「利益の話=PLの説明」にとどまっているという声をよく耳にします。
しかし、多くの中小企業では、いまだに税理士からの説明が「利益の話=PLの説明」にとどまっているという声をよく耳にします。
その背景には、税理士の仕事の根本に「納税」という役割があるからです。
利益が出れば税金が発生し、申告が必要になる。だから、税理士はどうしてもPLに目が向きがちになります。
けれども、今、本当に中小企業にとって必要なのは、「利益が出たか」ではなく「お金が残るか」という視点です。
現実には、赤字企業の割合が約7割とも言われる時代。
そんななかで問われているのは、どうやって資金繰りを安定させ、事業を継続していくか。 つまり、BSを通じて“お金の動きの全体像”を把握することが、経営者にとって最も切実なテーマになっているのです。
だからこそ、今の時代においてもPLしか語ってくれない税理士は、正直なところ、もう“古い”と言わざるを得ません。 経営者にとって頼れる税理士とは、「資金繰りの構造を一緒に見てくれる人」であり、「BSの変化を読み解いてくれる人」なのです。
縦断的分析とは?過去の財務から経営の“クセ”を知る方法
縦断的分析とは、同一企業の数年分にわたるBSを比較し、時間軸での財務の変化を見ていく分析手法です。
経営は常に変化していきます。売上が増えたり、借入が増えたり、設備を購入したり、従業員が増えたり。 それに伴って、資産の構成も負債の構成も変わっていきます。
しかし、単年のBSだけでは“何がどう変化してきたのか”は見えてきません。
そこで活用したいのが、この縦断的な視点です。
たとえば、現預金が減り、売掛金や棚卸資産が増えている。これは「売上は伸びているけど、資金が回収できていない」兆候かもしれません。
また、自己資本比率がじわじわと低下している場合には、「利益が出ていない状態が続いている」か、「過剰に借入に依存している」可能性もあります。
こうした“変化の兆し”に早く気づくことが、経営者の意思決定を助ける第一歩になるのです。
3期比較で見えてくる経営の傾向と改善のヒント
縦断的分析は、最低でも2期分、できれば3期以上のBSを用意しておこないます。
ポイントは、“今の数字”ではなく、“変化の流れ”を見ることです。 【ステップ1】3期分のBSを並べてみる
【ステップ1】3期分のBSを並べてみる
現預金・売掛金・棚卸資産・借入金・自己資本などの主要項目を並べて、増減と構成比の変化を確認します。まずは“額”を見ます。
【ステップ2】財務指標を確認する
自己資本比率・借入金依存度・流動比率・当座比率など、重要な指標の推移をチェックします。“額”だけではなく、“率”も大切です。
【ステップ3】数字の背景に目を向ける
「なぜ増えたのか?なぜ減ったのか?」という原因や背景を考えることで、数字に意味が宿ります。
【ステップ4】気づきを行動につなげる
変化の気づきが終わりではなく、「次はどうする?」という行動提案へとつなげることが、経営支援としての本質です。
縦断的分析は、「数字を並べる作業」ではありません。「数字で経営の物語を読み解く力」こそが、今、税理士に求められている視点なのです。
改善事例:数字を言語化して資金繰りを改善した企業
私の地元、山口県内で食品卸業を営むA社は、地元スーパーや飲食店向けに調味料や冷凍食品を販売している、社員15名ほどの中小企業です。
私と同世代の社長は営業畑出身の2代目で、売上拡大に積極的に取り組んでいました。 売上高は3年間毎年20%増加。利益も出ていたものの、資金繰りは年々厳しくなり、借入れが膨らんでいました。
売上高は3年間毎年20%増加。利益も出ていたものの、資金繰りは年々厳しくなり、借入れが膨らんでいました。
そこで、私が紹介したセカンドオピニオン税理士と一緒に過去3期分の貸借対照表を比較したところ、
① 売掛金が増加し、回収が遅延
② 在庫が過剰に積み上がり、資金が寝ている
③ 現預金が減少し、短期借入が増加
という状況が浮かび上がり、それを言語化して経営者と議論しました。
社長自身も「売上は伸びているのに、なぜ…」と違和感を持ちながら、明確に原因を説明できずにいたのですが、数字の“変化”を目の前にすると一気に腑に落ち、そこから在庫管理や与信ルールの見直しを進め、半年後にはキャッシュフローが改善。借入を抑えつつ、多額の手元資金を持てるようになりました。
数字は、「過去の行動を記録した“経営の足あと”」です。
それを一緒に読み解いてくれる税理士こそが、信頼されるパートナーとなるのです。
“伴走型の税理士”とともに未来を創ろう
BSを使った縦断的分析は、
「過去を振り返るための手段であると同時に、未来をつくるヒントにもなる武器」
です。
単年の数字に一喜一憂するのではなく、「変化の傾向」「企業のクセ」を把握し、それに基づいた行動がとれるかどうかが、これからの経営には求められています。
そして、その気づきを引き出してくれる税理士がいるかどうか。
これが、中小企業経営において非常に大きな差を生む時代になってきています。
PLだけを語る支援者ではなく、BSの変化を見て、資金の構造を読み解き、ともに未来を考えてくれる存在こそが、これから信頼される“伴走型の税理士”です。
BSの“変化”を一緒に見てくれるパートナー、あなたのまわりにいますか?

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。
趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。