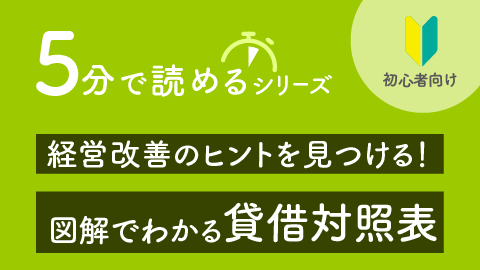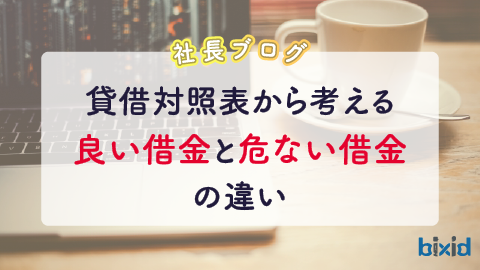中小企業の未来を左右する「資本構成の最適化」
こんにちは、YKプランニング代表取締役社長の岡本です。
自社の数字を見ていると、売上や利益に目が行きがちですが、経営の安定性と成長性を左右する「資本構成」を理解している経営者は、将来の選択肢がぐっと広がります。
今回は「貸借対照表の資本構成の最適化」というテーマで、中小企業がどのように安全性と成長性のバランスを整え、未来への選択肢を広げていくかを解説します。
資本構成とは?自社の体力を知る貸借対照表
貸借対照表には、企業が持つ資産と、その資産をどのような資金でまかなっているかが示されています。右側の「負債」「純資産(自己資本)」の割合こそが「資本構成」です。資本構成を理解することは、企業の経営基盤を理解することと同義です。
たとえば、自己資本比率が15%の企業と60%の企業を比べると、同じ売上規模でも資金繰りの安定性・信用力・成長余力が大きく異なります。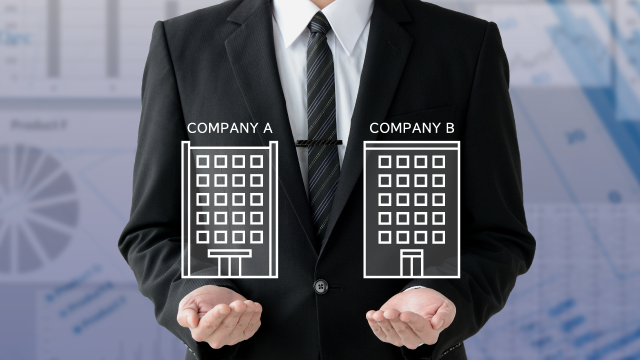 自己資本比率が15%程度というのは、中小企業では決して珍しくありませんが、やや心もとない状態といえます。金融機関から見れば、借入金への依存度が高く、内部留保が薄い企業と映り、追加融資や長期投資に慎重な対応を取られることもあります。
自己資本比率が15%程度というのは、中小企業では決して珍しくありませんが、やや心もとない状態といえます。金融機関から見れば、借入金への依存度が高く、内部留保が薄い企業と映り、追加融資や長期投資に慎重な対応を取られることもあります。
逆に、自己資本比率60%の企業は、借入に過度に頼らず、利益を内部留保として積み上げてきた状態であり、資金繰りや外部からの信用力の面でかなり安定しています。
中小企業の場合、特に創業・成長初期は借入への依存度が高くなりがちです。一方で、成熟期には内部留保が積み上がり、自己資本比率が上がってくる傾向があります。どのフェーズにおいても「いま自社がどんな資本構成にあるのか」を把握しておくことが、経営判断の土台となります。
最適化の本質は「守り」と「攻め」のバランス
資本構成の最適化というと専門用語のように聞こえますが、実際には自己資本と負債のバランスを整えることを意味します。ここでいうバランスとは、借入金を減らすことでも自己資本比率を上げることでもなく、企業の成長ステージに合わせて“ちょうどいい形に整える”ことです。
たとえば、自己資本比率が15%の企業は、資金繰りや金融機関からの評価の面でやや心もとない状態ですが、成長の伸びしろを感じる側面もあります。一方で60%程度の企業はかなり安定して見えますが、成長投資の機会を逃している可能性もあります。つまり、「高ければ良い・低ければ悪い」という単純な話ではなく、状況に応じて調整する発想が大切です。
ここでポイントになるのが、“時間軸”と“経営戦略”です。
たとえば、急成長のチャンスがある時期は、借入を活用して積極的に投資し、市場が不安定な時期には、内部留保を厚くして安全性を高める。経営戦略と時間軸に応じて資本構成を調整することが重要です。
この「守る」と「攻める」の切り替えこそが、資本構成の最適化の本質です。
また、バランスは一度決めたら終わりではありません。業績や市場環境、経営者の戦略によって、毎年・毎期見直しが必要です。「今年は内部留保を厚くする」「来年は借入を使って投資する」といった調整の積み重ねが、結果として“ちょうどいいバランス”を作ります。
こうした視点を持つことで、資本構成は「数字の結果」から「戦略の道具」に変わります。単に自己資本比率の高さを目標にするのではなく、「どのステージで、どのような構成にしておくか」を描ける経営者こそが、金融機関や投資家からも信頼される存在になれます。
借入は悪ではなく成長のためのツール
中小企業では、「借入=負債=悪いもの」というイメージが根強くあります。しかし実際には、借入金は経営を前に進めるための重要な“ツール”です。借入を戦略的に使うことで、自己資金だけでは実現できない成長や投資を可能にし、企業のポテンシャルを引き出すことができます。 たとえば、年商5億円の企業が新しい生産ラインに2億円を投資したいとします。自己資金だけでは時間がかかるか、そもそも実行できない規模かもしれません。ここで長期借入を活用すれば、短期間で投資を実行し、売上や利益の拡大を早期に実現できる可能性が高まります。将来キャッシュフローの見通しが立っていれば、金融機関も前向きに検討してくれます。
たとえば、年商5億円の企業が新しい生産ラインに2億円を投資したいとします。自己資金だけでは時間がかかるか、そもそも実行できない規模かもしれません。ここで長期借入を活用すれば、短期間で投資を実行し、売上や利益の拡大を早期に実現できる可能性が高まります。将来キャッシュフローの見通しが立っていれば、金融機関も前向きに検討してくれます。
借入のポイントは「資金の性質」と「調達の期間」を合わせることです。
・運転資金(短期資金)
仕入・人件費など日々の支払いに充てる → 短期借入・コミットラインで対応
・設備資金(長期資金)
工場・機械・システムなど長く使う投資 → 長期借入・リースでまかなう
こうした“マッチング”を意識するだけで、資金ショートや借り換えリスクを減らし、自社の信用力を高めることができます。
また、借入を活用することにはレバレッジ効果があります。自己資金だけで投資する場合に比べて、同じ資本でより大きな成果を狙えるため、ROE(自己資本利益率)が上昇し、投資家や金融機関からの評価が上がることもあります。ただし過剰なレバレッジは返済負担を増やし、経営を硬直化させるリスクがあるため、必ず事業計画・利益計画・返済計画を一体で検討することが不可欠です。
さらに、金融機関との関係づくりも重要です。決算書や試算表をタイムリーに提出し、資金の使い道と返済原資を明確に伝えることで、信頼が高まり、次の借入の条件が有利になります。借入を計画的に使って返していける企業という印象を持ってもらえることは、資本構成の最適化を進めるうえで大きな力になります。
実践のための3つのチェックポイント
資本構成の最適化は、まず「現状を正しく把握すること」から始まります。決算書を見るときに“売上や利益”だけでなく、“企業の体力”を示す貸借対照表に目を向ける習慣を持つことが大切です。ここでは、特に注目すべき3つの視点と具体的な行動を紹介します。
1. 自己資本比率の適正を確認する
自己資本比率は企業の安全性を示す重要な指標です。30~50%程度がひとつの目安で、15%程度ならやや心もとない状態、60%以上なら安定していますが、投資に慎重になりすぎている可能性もあります。現状の比率を把握し、経営戦略と照らして必要な調整を検討しましょう。
2. 借入の性質と期間を見直す
運転資金のような短期資金は短期借入で、設備投資など長期の資金は長期借入でまかなうなど、資金の性質と調達期間を合わせることが重要です。これにより資金ショートや返済リスクを減らし、経営の安定性を高められます。
3. 固定資産のカバー状況をチェックする
固定資産が自己資本+長期負債でまかなえているかを確認しましょう。短期資金で長期投資をしていると、思わぬ資金繰りリスクにつながります。定期的にチェックすることで、安全性と成長性のバランスを保てます。
この3つのチェックポイントをもとに、資本構成を整えるためには日々の習慣が大切です。まず、借入条件を定期的に確認し、金利や返済期間、保証条件を見直して、自社のキャッシュフローに合った形に整えましょう。次に、利益計画や配当方針をチェックし、成長投資や返済に必要な利益を内部留保として積み上げる仕組みを作ることが重要です。そして、決算後や中期経営計画のタイミングで、安全性と成長性のバランスを評価し、必要に応じて戦略を調整します。こうした小さな積み重ねが、資本構成をしっかりと安定させ、経営判断の力を高めてくれます。
こうして、「現状の見える化→調整→アップデート」を繰り返すことが、資本構成の最適化に直結します。数字を見ることが目的ではなく、“どう動くか”を決めるための道具にすることが大切です。
まとめ:資本構成を“経営戦略”に変える視点
資本構成の最適化は、単に「借入を減らす」「自己資本比率を上げる」といった数字の話ではありません。自社のビジョンや成長戦略に合わせて、資金調達と内部留保のバランスを整えるプロセスです。
経営環境や戦略に応じて、守るときと攻めるときがあり、最適な資本構成は固定されません。だからこそ、貸借対照表を定期的に確認し、必要な調整を繰り返すことが重要です。
資本構成を経営の舵取りのツールと考えると、銀行や投資家との信頼も深まり、将来の資金調達や投資機会の幅が広がります。数字の結果ではなく、意思決定の道具として活用すること──これが資本構成最適化の本当の価値です。

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。
趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。