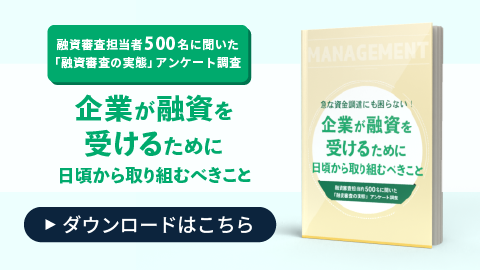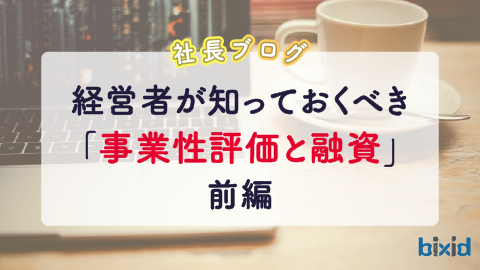経営者が知っておくべき「事業性評価と融資」後編
(監修:日下智晴)
こんにちは。YKプランニング代表取締役社長の岡本です。
前回のブログでは、事業性融資の基本的な説明や「事業性融資推進法(事業性融資の推進等に関する法律 法律第52号)」制定の背景や目的、そして「認定事業性融資推進支援機関」について解説いたしました。まだ読まれていない方はこちら【前編】を先に読んでいただくことをおすすめします。
【後編】では、法律の制定に伴い新たに導入される「企業価値担保権」とはなにか、そして中小企業における影響について解説いたします。
企業価値担保権とは?何が担保になるのか?
事業性融資推進法(事業性融資の推進等に関する法律)では、新たな「企業価値担保権」の導入も重要なポイントです。
企業価値担保権とは、会社が持っている「企業価値」を担保として、資金調達を行う仕組みです。通常、担保としては不動産や設備などの物的資産が使われますが、企業価値担保権では、企業の将来の成長性やブランド力、顧客基盤などの無形の価値をもとに資金を借り入れることができます。
企業価値担保権の対象となるのは、具体的に以下のようなものが想定されます。これらの要素を評価し、金融機関がそれを担保として認めることで、資金を調達することが可能となります。
①将来の収益力・・・過去の業績や市場の成長予測に基づいた将来の収益
②顧客リストや取引先リスト・・・長年培ってきた顧客や取引先との関係性
③ブランド価値・・・業界内での知名度や信頼度
④知的財産・・・特許や商標、技術的なノウハウ
企業価値担保権のメリットと課題
中小企業にとって、物的資産が少ない場合でも、この企業価値担保権を活用することで資金調達の幅が広がります。特に、成長性のある企業や、ブランド力が強い企業にとっては、これを活用することで、さらなる事業拡大のための資金を得やすくなります。
また、金融機関にとっても、企業の本質的な価値を評価し、リスクを軽減しながら融資を行うことができるというメリットがあります。
しかし、企業価値担保権の根幹は無形資産や将来の収益力など、目に見えない価値にあり、評価が難しいため、金融機関による査定にばらつきが生じる可能性があります。特に、中小企業の場合、実績や市場データが十分でないことが多く、正確な評価が難しくなります。
また、物的資産のように明確な担保がないため、金融機関にとってはリスクが高いと考えられることがあります。そのため、慎重な審査が行われる可能性があり、結果として資金調達が難航することもあります。
企業価値担保権は新しい概念であり、法的な整備がまだ十分ではない部分があります。特に、担保権の実行方法や優先順位などについて、明確なガイドラインがまだまだ不足しています。
そのため、企業価値担保権の概念が市場に広く受け入れられるまでには時間がかかることが予想されます。特に、金融機関その他企業を取り巻くステークホルダーの理解が進まない限り、実際の利用がなかなか進まない可能性があります。
また一方で、中小企業の経営者が、自社の無形資産の価値を理解し、それを担保として利用する意識がまだ低いことも大きな課題です。企業価値担保権を効果的に活用するには、経営者自身が無形資産の管理と活用に対する意識を高める必要があります。
企業価値担保権は、中小企業にとって大きな可能性を秘めていますが、その実現にはいくつかの課題があります。特に、価値評価の難しさや法的整備の未成熟さは、今後の普及に向けて解決すべき重要なポイントです。
これらの課題に対処しながら、企業価値担保権の活用を推進していくことが求められます。
中小企業への影響
事業性融資推進法が2024年6月14日に施行され、事業性融資の推進や企業価値担保権の設定に関する新たな枠組みが整備されることで、中小企業の資金調達がより柔軟かつ多様な方法で行える時代が始まります。
中小企業にとっては、今後は将来の収益力や事業計画を基にした融資が可能となり、成長のための資金確保がより容易になるでしょう。
また、金融機関の融資方針も変わることが予想されます。この法律により、金融機関は従来の担保重視の融資方針から、事業性を重視した融資方針へと転換することが求められます。
これにより、金融機関は中小企業の事業計画や未来の収益力をより深く評価し、それに基づいて融資を行うようになるため、金融機関自身のリスク管理能力や評価スキルの向上が重要になります。
さらには、企業価値担保権が法的に明確化されることで、中小企業は自社の無形資産、例えば知的財産やブランド価値を担保として利用することが可能になります。これにより、従来の物的担保に依存しない新たな資金調達手段が普及する可能性があります。 中小企業にとって、この法律の施行は経営改善のチャンスです。
中小企業にとって、この法律の施行は経営改善のチャンスです。
事業性融資が普及することで、中小企業は短期的な利益追求から脱却し、より長期的な視点の経営に変化します。将来的な成長を見据えた事業計画の策定が求められ、経営の質が向上することが期待されます。また、金融機関からのアドバイスや支援も期待でき、経営改善につながるでしょう。
さらに、管理会計の重要性は一段と高まります。
中小企業が将来の収益力や事業性を明確にするためには、管理会計が重要な役割を果たします。この法律の施行により、管理会計の導入や活用が促進されることで、企業内部での財務管理や経営判断の精度が向上し、経営の透明性が高まることが期待されます。
そして最も大切なことは、「経営者の意識改革」です。
従来の物的担保に依存する資金調達から脱却し、企業の成長や将来の収益性を重視する意識が求められるようになります。つまり経営者が自身の企業の強みを再認識し、それを活かした事業計画を立てることが、ますます重要になるということです。
「事業性融資推進法」は中小企業にとってのチャンス
「事業性融資の推進等に関する法律」は、中小企業の経営に新たな風を吹き込む画期的な法制度です。これまでのように物的担保に頼るだけではなく、企業の将来性や事業性を評価することで、より柔軟で持続可能な資金調達が可能になります。これは単なる資金調達の手段が増えるということだけでなく、企業の経営戦略そのものに変革をもたらす可能性を秘めています。
経営者の皆様にとって、この法律の施行はまさにチャンスです。
自社の未来に向けたビジョンをしっかりと描き、それを金融機関と共有することで、これまで以上に強固なパートナーシップを築くことができます。企業価値担保権の活用や事業性融資を通じて、今まで眠っていた企業の潜在力を引き出し、次なる成長へとつなげることができるでしょう。
この変化に対応するためには、経営者自身の意識改革も必要です。
未来を見据えた長期的な経営戦略を立てること、そしてそれを実現するための計画をしっかりと管理することが求められます。管理会計の導入や、自社の強みを最大限に活かす戦略の策定は、その第一歩です。経営者の皆様がこのチャンスをしっかりと捉え、企業の未来を切り拓いていくことを強く期待しています。
今こそ、変革の時です。
皆様の勇気ある決断が、企業の未来を輝かせることを信じています。共に、未来に向けて歩み出しましょう。

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。
趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。