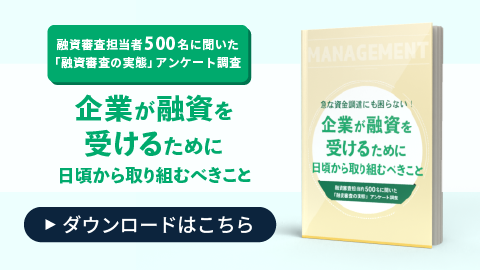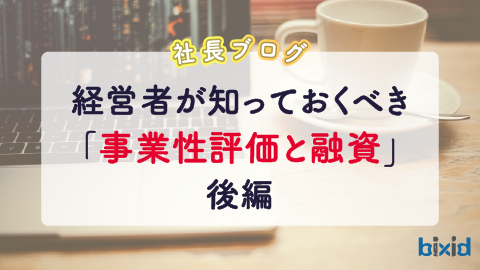経営者が知っておくべき「事業性評価と融資」前編
(監修:日下智晴)
こんにちは。YKプランニング代表取締役社長の岡本です。
「銀行からの融資を受けるには、結局のところ決算書の数字がすべてなんでしょう?」
そう思われている方も多いかもしれません。確かに、財務状況は融資審査の重要なポイントですが、それだけではありません。最近では、金融機関が「事業性評価」という視点を重視するようになっています。
昨年の2024年6月14日に「事業性融資推進法」(事業性融資の推進等に関する法律 法律第52号)が公布されました。この法律は、「公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされています。つまり2026年の12月までには施行されることが決まっています。この法律の誕生により、従来の融資方法に変革をもたらし、中小企業にとってより柔軟な資金調達の機会が増えることが想定されます。
本ブログでは事業性評価・事業性融資とはなにか、そして新しく制定された「事業性融資推進法」について、中小企業経営者の目線に立ち【前編】【後編】の2回に分けて、わかりやすく解説します。
事業性融資とは?
新しく制定された「事業性融資推進法」における事業性融資とは、
「金融機関等からの会社に対する貸付けのうち、不動産を目的とする担保権又は第十二条第四項に規定する個人保証契約等(同項に規定する停止条件が付された契約その他の主務省令で定めるものを除く。)若しくはこれに準ずるものとして主務省令で定めるものによって担保されず、又は保証されないものをいう」(第二条第一項)
と記載されています。
条文なので堅苦しい文章になっていますが、これを企業目線でわかりやすく表現しなおすと、「決算書や試算表の過去の実績、さらには不動産担保や保証人で融資の判断をするのではなく、企業の事業内容や将来性を考慮して行う融資」という感じになります。 事業性融資は、中小企業が安定して事業を続け、成長を目指すために必要な資金をスムーズに調達できるよう、企業と金融機関がしっかりと連携して進められるべきものです。
事業性融資は、中小企業が安定して事業を続け、成長を目指すために必要な資金をスムーズに調達できるよう、企業と金融機関がしっかりと連携して進められるべきものです。
この法律を円滑に推進するために金融庁に特別の機関として「事業性融資推進本部」を置くことが決められていて(第二百四十二条)、推進本部では基本的な政策の企画や立案を行い、関係行政機関の事務を調整することが定められています。
事業性融資推進法の背景と目的
事業性融資推進法(事業性融資の推進等に関する法律)は、日本の中小企業が抱える資金調達の課題に対応するために制定されました。この法律の背景には、特に中小企業が将来の成長を見据えた資金調達に困難を感じているという現実があります。
①法律制定の背景
日本における従来の融資制度は、主に「担保や保証人」を重視したものでした。これは、「現時点での企業の財務状況や資産価値」に基づいて融資の可否を判断する傾向が強いことを意味します。このアプローチは、確かに安全性が高い一方で、成長途上にある企業や、新たな事業展開を目指す企業にとっては、資金調達が困難になるという問題点を抱えていました。
特に、無形資産を多く保有し、将来の収益性が高いにもかかわらず、現時点での担保が不足している企業に対しては、融資が行われにくい状況が続いていました。
②法律の目的
この法律の目的は、「企業の将来の収益性や事業の成長性を重視した融資制度を整備し、経済の持続的な成長を促進すること」です。これにより、企業が持続可能な成長を遂げるための資金調達手段として、事業性融資が広く普及することを目指しています。
③具体的な施策
事業性融資を行う金融機関は、企業の事業計画や将来のビジョンを適切に評価し、それに基づいて資金供給を行うための基準やガイドラインを整備することが求められてきます。さらには、企業の成長性や収益性に基づく融資を行うための新しい基準を策定し、企業の持続可能な成長をサポートすることが期待されています。
事業性融資を行うにあたり、企業の経営計画策定支援を推進することが重要であり、企業と金融機関が協力して、経営の質を高めるための支援を行う仕組みが強化されることが目的とされています。
④中小企業にとってのメリット
中小企業にとって、この法律の制定は「資金調達の選択肢が広がる」ことを意味します。特に、事業の成長段階にある企業や、新たな事業分野に進出しようとする企業にとって、この法律に基づく事業性融資は、必要な資金を確保するための重要な手段となります。また、金融機関が企業の将来性を見据えた融資を行うことで、企業が持続的な成長を遂げるための基盤が強化されることが期待されます。
認定事業性融資推進支援機関とは?
この法律では、「事業性融資推進支援業務を行う者」の認定制度が導入されました。(第二百三十二条)この認定を受けたものを「認定事業性融資推進支援機関」と呼びます。
認定事業性融資推進支援機関は、金融機関と中小企業の間に立ち、円滑な融資をサポートします。中小企業にとって、こうした認定支援者の存在は、より適切な資金調達の実現に寄与する重要なパートナーとなるでしょう。
事業性融資は、企業の成長や事業の継続に必要な資金調達を円滑に進めるための重要な手段ですが、その利用には一定の専門知識やスキルが求められます。そのため、事業性融資の推進をサポートするプロフェッショナルが必要となります。
この役割を担う有力な候補として、会計士や税理士、中小企業診断士、経営コンサルタントなどが挙げられます。特に、彼らは企業の財務状況や経営課題を深く理解しており、適切な助言をおこなうことができる専門家です。
ここでのキーワードは「管理会計」です。管理会計は、企業内部の経営資源を最適に配分し、効率的な経営を行うための会計手法であり、事業性融資の活用においても極めて重要な役割を果たします。

認定事業性融資推進支援機関は、管理会計の知識を活用し、中小企業が資金を有効に活用して事業を成長させるための戦略的な助言を提供することが求められます。具体的には、企業の経営計画の策定支援や、融資を受ける際の財務分析の提供、さらには融資後の資金の管理や運用に関するモニタリングなどが含まれます。
会計士や税理士、中小企業診断士、経営コンサルタントがこの業務に従事することで、中小企業は自社の財務状況をより深く理解し、事業性融資を最大限に活用することができるようになります。これにより、企業の成長や発展が促進されるだけでなく、健全な経営基盤を築くための一助となるのです。
中小企業の未来を広げる「事業性融資推進法」
今回は「事業性融資推進法」の基本について解説しました。この法律の施行により、金融機関は財務数値だけでなく、企業のビジネスモデルや成長可能性を重視するようになります。そのため、中小企業にとっては、自社の強みや将来の展望を的確に伝えることが、資金調達の成功に直結する重要なポイントとなります。事業計画書の作成や、金融機関との対話の仕方にも工夫が求められるでしょう。
後編では、企業価値担保権の設定や、この法律が中小企業の融資環境に与える影響について詳しく解説します。今後の資金調達をスムーズに進めるためのヒントもお伝えするので、ぜひご覧ください。

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。
趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。