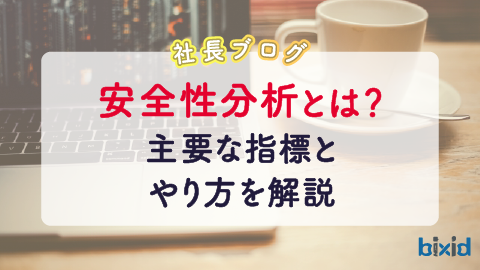資金力分析とは?主要な指標とやり方を解説
こんにちは。YKプランニング代表取締役社長の岡本です。
今回は、財務分析の4つの柱「収益性」「安全性」「資金力」「効率性」の中から「資金力」について深掘りしていきます。
資金力分析とは?何がわかるのか?
財務分析における「資金力」とは、企業がどれだけの現金または現金同等物を生み出し、維持できるか、そしてそれをどれだけ効率的に活用しているかを指します。 これにより、企業が成長や拡大に必要な資金を確保し、財務リスクに対処する能力を判断します。
これにより、企業が成長や拡大に必要な資金を確保し、財務リスクに対処する能力を判断します。
なぜ資金力分析が重要なのか
資金力の分析は、企業の持続的な成長能力と財務健全性を把握するために不可欠です。強固な資金力を有する企業は、不測の事態や市場の変動に柔軟に対応しやすく、戦略的な投資も積極的におこなえます。
資金力を測る主要な3つの指標
ここでは資金力を測る指標として以下の3つについて解説していきます。
①キャッシュフロー額(≒EBITDA)
企業の基本的な営業活動からどれだけの現金が生み出されているかを示します。
減価償却費やその他償却費は実際に現金が出ていくわけではないため、これらを営業利益に加算することで、実際に企業が稼ぐ力、つまり現金を生み出す能力を把握できます。
※詳しくは「EBITDAとは?基礎から詳しく解説!」のブログをご覧ください。
②債務償還年数
企業が現在のキャッシュフローを維持した場合に、全ての借入金を返済するのに要する年数を示します。
③借入金対月商倍率
企業の借入金が月間の売上高に対してどれくらいの割合を占めるかを示す指標です。企業がどれだけの売上で借入金を返済できるかを示します。
各指標の計算方法と数値の見方
①キャッシュフロー額= 営業利益 + 減価償却費 + その他償却費(単位:円)
企業の運転資本や投資、債務返済などに利用可能な現金の量を計る指標として用いられ、企業の資金力を評価するうえで重要な基準となります。適正な数値は業種や企業規模により異なります。一般的には前年比で増加している状態が望ましいとされます。
前年比で減少している、または期待値を下回っている場合、企業の収益性や現金生成能力に問題がある可能性があります。これは運転資本の不足、投資機会の損失、あるいは借入金の返済能力の低下に繋がる恐れがあります。
②債務償還年数 = 総借入金額 / 年間のキャッシュフロー額(単位:〇年分)
企業の借入金に対する返済能力を評価するために使用されます。年数が短いほど、企業は迅速に借入金を返済できるため、財務的に健全であると評価されます。一般的に、債務償還年数は3年から5年以内であることが望ましいとされます。これは、企業が中期的な期間内に負債を返済できる健全な財務構造を持っていることを示します。
債務償還年数が5年を超える場合、企業は過剰な借入による財務圧力が高い状態にあると考えられます。長期間にわたる高い財務負担は、資金繰りの悪化や投資機会の逸失を引き起こし、企業成長に悪影響を与える可能性があります。
③借入金対月商倍率 = 総借入金額 / 月平均売上高(単位:〇か月分)
この比率が低ければ低いほど、少ない売上で借入金を返済できることを意味し、企業の資金繰りが良好であることを示します。適正な比率は業界によって大きく異なりますが、一般的には3か月以下であることが望ましいとされます。これは、企業が3か月分の売上高で全借入金を返済できることを意味し、良好な資金繰りを示します。
6か月を超える場合、企業は売上に対して過剰な借入をしている可能性があり、財務リスクが高まります。この数値が高い企業は、市場の変動による売上の減少時に、返済負担が重くなり資金繰りに苦労する恐れがあります。
企業における資金力分析の活用例
資金力分析結果は、キャッシュフローの状況を正確に把握し、経営の意思決定をより効果的に策定することが可能となります。 ①経営戦略の策定
①経営戦略の策定
キャッシュフローが安定しており、余剰資金があることがわかった場合、積極的な投資や事業の拡大にチャレンジすることができます。逆に資金繰りに課題があることが明らかになれば、コスト削減や資産の売却、追加資金の調達など、早めの意思決定をサポートしてくれます。
②財務リスクの管理
債務償還年数や借入金対月商倍率の指標を用いることで、返済能力や持続可能性を評価することができます。これらの指標が示すリスクを理解することで、返済スケジュールの見直しや借り換え、あるいは財務構造の最適化など抜本的な対策を後押ししてくれます。思わぬ売上減や予期せぬリスクから自身を守るための重要な情報となります。
③投資機会の評価
資金力分析は、新たな投資機会を検討する際にも重要な役割を果たします。キャッシュフロー額を正確に把握することで、新たな投資によってさらに生み出される資金を予測し、投資の妥当性を判断することが可能となります。また適正な借入額や利息負担など、リスクとリターンのバランスを考慮したうえで、最適な価値を生み出すための投資判断が可能となります。
まとめ
資金力は、企業の成長と持続可能性を支える重要な要素です。財務分析を通じて資金力を定量的に評価し、その結果を経営戦略の策定に活かすことで、企業はより効率的に資源を管理し、市場での競争優位性を確立することができます。
資金力が高い企業は、経済状況の変動や市場の不確実性に柔軟に対応し、持続的な成長を達成するための強固な基盤を持っています。そのため、財務分析は一度きりではなく、定期的におこなうべきです。
市場環境や企業の事業モデルが変化するにつれて、資金力に関する指標も変動します。したがって、企業はこれらの指標を継続的にモニタリングし、得られた知見を必要に応じて経営戦略に反映させることが重要です。これにより、企業は不測の事態に対応し、長期的な財務健全性と成長を実現することができます。

1998年3月山口大学経済学部卒業。学校法人大原簿記法律専門学校入社。簿記・税理士講座の講師を務めた後、2003年行本会計事務所に入所。2017年株式会社YKプランニング代表取締役社長就任。ミッションである「独りぼっち経営者を0に」実現のために日々奮闘中。
趣味は長距離運転、スキンダイビング(素潜り)、GoogleMAPを見ること。