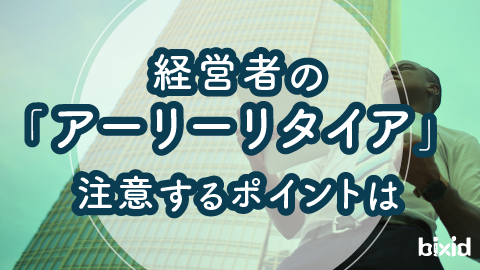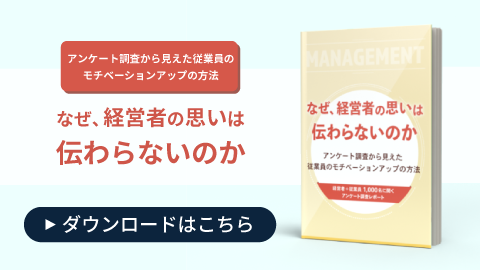後継者探しと後継者育成のための取り組み
こんにちは、YKプランニング管理本部長であり公認会計士の丸山です。
経営者の皆様は、現在、後継者育成のために何か取り組みをされていますか?
後継者は、候補を見つけるのも大変で、見つけた後に育てることはもっと大変です。
とにかく、適切に後継者を育成するにはめちゃめちゃ時間がかかるわけです。
2021年の帝国データバンクの調査によると、全国の『後継者不在率』は61.5%という結果で、半数以上の企業が後継者不在という状況です。
参考:帝国データバンク 全国企業「後継者不在率」動向調査(2021年)
そのため、近年では黒字でありながら『後継者不在による事業廃業』を選択する企業も多いようです。どうしてこのようになるのでしょうか?
それは、準備が遅いことが一因でしょう。
少なくとも、現経営者が高齢になり、仕事が思うようにできなくなったタイミングで後継者を探すのでは遅いですよね。
仮に、時間をかけずに勢いで後継者を見つけ、事業承継したとしましょう。
その場合、明らかに会社がうまく回らないでしょう。
利益が下がるどころか、赤字に転落することもよくあることです。また、従業員は、現経営者と比較しますから、後継者の資質や能力を深く洞察してきます。能力が不足していると認定されれば、離職することもあるでしょう。
やはり、後継者の選定と育成は時間をかけてしっかりと検討していく必要があります。
今回は、後継者候補が経営者に向いているかどうかを事前にチェックし、不足している能力をどう補い、育成していけばいいのか、ステップごとにご紹介します。
後継者探しと後継者育成のためのステップとは?
先に申し上げておきますが、後継者探しと後継者育成のための取り組みは、次の4つのステップだけで十分です。これ以上のことを深く考えてもきりがありません。
まずは、4つのステップを整理することからスタートしてみましょう。 【Step1】 後継者候補を探そう
【Step1】 後継者候補を探そう
【Step2】 後継者に社内の各部門の経験を積ませよう
【Step3】 現経営者が直接指導しよう
【Step4】 会計インパクトを読み取る力をつけよう
【Step1】 後継者候補を探そう
最初のステップは『後継者候補を探すこと』から始まります。
とはいえ、どのような選定基準で後継者候補を探せばよいのでしょうか?
例えば、一般的な資質・能力として次のようなポイントがあげられます。
・経営に対する意欲・覚悟
・経営・会計に関する知識・実務経験
・自社の事業に関する専門知識・実務経験
・社内外でのコミュニケーション能力
・血縁関係
・企業文化などの理解度
などを基準にして、具体的に候補者を探してみましょう。選定基準は最低5つのポイントがあるとよいでしょう。
後継者候補が1人の場合は迷うことはありません。ですが、複数の候補者がいる場合は、選定基準ごとに点数をつけ、各候補者の資質・能力を可視化してみましょう。
最終的には1人に絞ります。まんべんなく点数の高いバランスタイプを選んでもいいですし、総合力は不足していても、何か特別な能力を持つタイプを候補者として選んでも問題ないでしょう。
選択は現経営者の自由です。選定プロセスの中で、候補者の資質・能力を可視化させたうえで、最終的に自身の決定に納得感があるかが重要です。
候補者に不足している能力は、時間をかけて育成すればよいのです。
【Step2】 後継者に社内の各部門の経験を積ませよう
次のステップは、後継者に『社内の各部門の経験を積ませる』ことでしょう。
後継者が現在所属している部門以外の経験を積ませることから始めましょう。
例えば、技術部門所属の後継者ならば、営業部門や管理部門(財務、経理、人事)といった部門を中心に、3か月スパンでもいいので、さまざまな部門をローテーションして経験を積ませるということです。
目的は、社内でのあらゆる業務をおこなうことで、現場の感覚が身につくからです。また、何より会社全体を俯瞰して捉えることができるようになります。経営者には、組織を持続的に全体最適に導く能力が求められます。
現経営者は、創業の時期にすべての会社の業務を自身でおこなっていることも多く、そもそも組織全体をとらえる能力が備わっています。
一方で、後継者は自部門だけの部分最適に力を発揮できても、会社全体を見渡せる人材は少ないため、ローテーションの経験は会社経営の舵取りに必ず効果を発揮します。
さらに、ローテーション期間に、従業員と同じ目線で仕事と向き合い、積極的にコミュニケーションを取り、社内の支持を集めておくことも重要です。そうすることで、現経営者が引退しても、会社から離れる従業員が少なくなります。
【Step3】 現経営者が直接指導しよう
3番目のステップは『現経営者が直接指導をおこなう』ことでしょう。
これは、後継者に経営幹部として参画させ、現経営者の意思決定プロセスを吸収させることが目的です。例えば、経営上の重要な意思決定会議に参加させたり、対外的な交渉について経験を積ませたりすることがあげられます。
意思決定や交渉を最初から上手くできる人は少ないです。なので、意思決定のポイントを丁寧に引き継ぎし、対外的な交渉の場に連れて行くなどして、現経営者がどのような交渉をおこなっているのかを実際に見せるのも効果的です。ときには交渉を思い切って任せることも必要でしょう。
このような経験を後継者にできるだけ多く積ませ、現経営者がひとつひとつ直接指導をおこなうことにより、後継者の責任感やリーダーシップが自然と生まれてきます。
【Step4】 会計インパクトを読み取る力をつけよう
最後のステップは『会計インパクトを読み取る力をつける』ことです。
会社は、経営者の意思決定に基づき対外的な取引をおこないます。また、時には事業撤退や従業員のリストラなど厳しい判断を求められることもあります。これらは、すべて会計数値にインパクトを与えます。
「私にはどれほどの金額の影響があるか分かりません」では、後継者の能力不足を感じます。
数字を読み取れない経営者は、確実に正しい判断ができません。
そのため、『【Step3】現経営者が直接指導しよう』で述べた意思決定や交渉ごとは、必ず会計数値に与える影響額を計算できるように習慣づけましょう。
最終的には、数字に敏感な経営者ほど会社は持続しますし、数字に無頓着な経営者ほど会社を倒産させてしまうことも多いです。
まとめ
後継者探しと後継者育成のポイントは、ズバリ『できるだけ早めに取り組む』ことでしょう。
現経営者の交代はいつ起こるかわかりません。「まだ若いから大丈夫」と思っている経営者でも、急な状況の変化で交代を余儀なくされることもあります。
そして、もう一度言いますが、後継者探しと後継者育成にはめちゃめちゃ時間がかかります。
付け焼き刃の事業承継をしても、明らかに会社はうまく回らないですし、会社は倒産に近づくだけです。
会社は継続してこそ価値があるのです。
そのため、後継者育成はできるだけ早めに取り組みたいものです。
このブログを読み終えた現経営者の皆様、さっそく後継者候補を探し、後継者育成の一歩目を踏み出してみませんか?